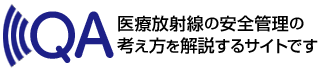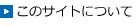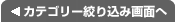No. 234 医療法とRI規制法の二重規制
医療法と放射線障害防止法の規制の一元化の議論の経緯を教えて下さい。
医療放射線管理の充実に関する検討会報告書(平成8年3月)
当時の厚生省医薬安全局長が招集した医療放射線安全管理に関する検討会(第1回)(平成10年1月16日開催)でも資料として配付されています。
一元化すべき放射線装置・器具の範囲(2ページ)
放射性同位元素を装備した装置・器具、高エネルギー放射線発生装置について、医療法において一元化を図ることが適当である。なお、高エネルギー 放射線発生装置については、設置台数や医療機関の数が多く、二重規制により負担を軽減すべきとの要望も強い。
その議論に沿った意見例
放射線安全規制検討会中間報告書(案)に寄せられた意見
医療放射線防護連絡協議会からの意見には、昭和52年12月に閣議決定された「行政改革の推進について」からの経緯が解説されています。
照射器具についてその方向性は難しいと判断された例
「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)における決定内容
医療法とRI法の関係に関する通知例
医療法上の手続と放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(現在は、放射性同位元素等の規制に関する法律)上の手続との関係について(医政発第0601003号. 平成17年6月1日)
医療法上の手続と放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律上の手続との関係について(昭和四五年四月一〇日)
医療法上の手続と放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律上の手続との関係について (医発第605号. 昭和39年5月15日)
RI法の規制整備
原子力規制委員会.放射性同位元素使用施設等の規制に関する検討の進め方(案)(平成28年5月25日)
規制整備に向けた関係者会合
薬機法
解説資料例
【相談事例 6】医療放射線安全管理委員会〈医療法〉と放射線安全委員会〈RI 法〉について
帳簿の合理的な運用
関連Q&A
一元化を目指した意見例
修正・追記を求める内容
中間報告書(案)の「今後の方針」に示されているように、現在、医療分野における放射線利用に対しては、放射線障害防止法と医療法(医療法施行規則)により規制されており、一部は二重規制となっております。そのため、「許認可手続き等を合理化する趣旨から、医療法で必要な措置を講じた上で、医療法に一元化することを可及的速やかに行うべきである。」との追記を要望いたします。
その理由・根拠
現行の放射線安全管理上の問題点は、医療分野における二重規制であり、そのために様々な面で煩雑な事務処理がなされていることは否定できません。一例を上げれば、放射線発生装置等は、放射線障害防止法の規制対象となるため許可申請が必要であり、かつ、医療法上でのあらかじめの届出も必要です。そのために、放射線障害防止法に基づく放射線検査官による立入検査と医療法に基づく医療監視が実施されているのが現状です。これらの実情を踏まえ、医療分野においては、その使用目的を鑑み、医療法で一元化するような放射線管理体制を構築することが今後必要であると思われます。また、医療法での規制となった場合には、行政における医療監視員(立入検査官)が第1種放射線取扱主任者レベルの知識や技術を持つよう、資質を向上させることが重要であることと思います。