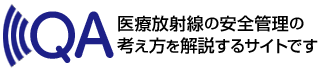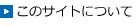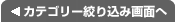No. 330 救急処置室への据付型エックス線装置の設置
救命救急センター機能を充実するため、救命救急処置室へ据付型エックス線装置の設置を検討し、保健所に医療法第7条第2項に基づく「病院開設許可事項の一部変更申請」を行いましたところ、医療法施行規則第30条の14の「使用場所の制限」の理由により申請が受理されず、ポータブル装置で対応せざるを得ません。他県の救命救急センターでは許可されているのですが、何故、本県では許可されないのか理由をご教示ください。
この記事は、「医療放射線管理についてのQ&A」日本放射線技師会雑誌から許諾を得て転載しています。
回答1(広島県立神石三和病院 清堂 峰明)
【救命センター救急処置室への据付型エックス線装置設置の許可要件】
救急処置室でエックス線撮影は日常的におこなわれています。ほとんどの場合、移動型エックス線装置が使用され、放射線防護に関する諸問題やエックス線装置の許可、届出には苦慮することが多いのが実情です。
表題のように、救急処置室へ据付型エックス線装置を設置する場合の許可要件について述べますが、基本的に、移動型エックス線装置であろうと使用頻度によっては、据付設置と同じようにエックス線診療室としての要件を満たし、各種の標識を付けることを義務付けるべきだと思います。ゆえに、救急処置室をエックス線診療室として許可を受ける必要があるのは、据付型エックス線装置を設置した場合、また、移動型エックス線装置の使用頻度が高い場合となります。その使用頻度の目安は救急処置室の隔壁での線量が1.3mSv/3月(2.5μSv/h)を計算で越えるようであれば、あわせてエックス線診療室としての許可も受けるべきだと考えます。ただ、移動型エックス線装置を据え置き型として許可する場合、医療法施行規則第30条の4第2項 「エックス線診療室内には、エックス線装置を操作する場所を設けない。」に抵触しますが、放射線照射時には、適当な防護物等を設けることなどの措置を講じ、救急処置室全体としての放射線防護を確保した方が、放射線の安全利用の観点から効果的だと思われるからです。
【許可要件】
(1)エックス線撮影の適用
- ・エックス線照射の対象患者は、エックス線診療室までの移動が困難で救命が最優先される患者。
- ・また、撮影のための移動により予後のQOLに著しく影響を及ぼすと予想される患者に限り、救急処置室であることを鑑み、必要最低限の撮影に限る。
- ・透視はおこなわないこと。(一般撮影に限る)
- ・同室内に二台以上のエックス線管を備える場合は、複数のエックス線装置から患者に対して同時にエックス線照射をおこなわないこと。
- ・同時に二人以上の患者の撮影はしないこと。
(2)エックス線撮影時の防護
- ・エックス線装置の操作は別室でおこなうこと。
- ・エックス線装置を直接操作する医師、診療放射線技師は放射線診療従事者として登録し,個人被ばく線量計を着用すること。
- ・処置にあたる医師・看護師等は放射線診療従事者として登録し、個人被ばく線量計を着用すること。
- ・撮影介護者および患者から離れることのできない者は、0.25mmPb以上の防護衣等を着用すること。患者から離れることのできる従事者は、防護衝立等の防護措置を講じた場所に退避すること。
回答2(大阪府泉州救命救急センター 坂下惠治)
【据付型エックス線装置を設置する施設として】
当センターは平成6年10月に開設した独立型の救命救急センターで、南大阪全体と関西空港に対する災害拠点病院として三次救急医療を実施しています。救急処置室には天井走行型のエックス線管保持装置を設置し、救急患者の搬入時にはその装置を用いてエックス線撮影を行っています。
開設時に行った許可申請では、救急処置室兼エックス線室という名称を用いて管理区域として申請し、表示灯、標識、遮蔽構造、1.5mmPb鉛ガラスを使用して規格は法令に準拠し、さらに遮蔽用鉛衝立の設置など安全面に配慮して開設の準備をしました。現在、救急処置室では移動型エックス線装置を用いて撮影を行うのが一般的ですが、当センターでは重症患者を診療する機会が多いことから汚れの広がる可能性がある床面に接する機材を極力少なくし、エックス線撮影が他の緊急処置を極力妨げないよう天井走行型エックス線管保持装置を導入しました。さらに、この装置にはCアームが装備され、X線束が鉛直方向の撮影時は患者を安静にしたまま撮影が可能で、X線束が水平方向の撮影時にはカセットと患者をアームが保持することから介助者が不要となり、無用な被ばくを防いでいます。また、救急処置室以外に一般エックス線撮影室を設置し、入院中に行う経過観察の撮影や緊急を要さない患者の撮影はその撮影室を用いるようにし、救急処置室のエックス線撮影を制限しました。
【他の救急処置室の事例】
米国では、救急処置室における据置型エックス線装置の導入実績は見あたらず、未だに救急処置室では移動型エックス線装置を用いて撮影を行っています。しかしながら、John H. Stroger Jr. Hospital of Cook Countyのように高度に救急医療に特化した施設では、外傷センターの一角に管理区域として区切られたエックス線撮影室を持ち、フラットパネルを装備した一般撮影用Cアーム装置を用いて撮影する環境は用意されています。
本邦でも、近年外傷センターとして取り囲むように処置室を配置する施設は出来つつありますが、急性期救急患者に用いるための独立した一般撮影室を設置する施設は見あたらないのが実状です。
【個人被ばく線量測定の結果】
職員の個人被ばく線量測定については、管理区域で診療業務に従事する医療スタッフは全て個人被ばく線量計を持つことにしました。救命センターの場合、医療職は夜間業務に従事するため特殊健康診断を実施するのは比較的容易といえます。5年以上勤務する医療職の5年累計被ばく線量は最高値が4.0 mSv(診療放射線技師)で、医師の平均5年累計被ばく線量は0.35mSvでした。当センターでは年間1000件程度の救急患者を受け入れていますが、輻湊する患者の搬入が極めて少ないこと、エックス線撮影時には遮蔽物の後方に待避する習慣が定着していること、撮影時に患者の介助をする医師数が10名程度いること、Cアームがあるため介助の頻度は少ないことなどが個人被ばく線量を低くした要因と考えます。
【救急患者の初期診療と撮影について】
搬入早期の救急診療は、重傷であればあるほど画像診断の適応は制限を受け、多数の部位、および方向を撮影することは必要としません。外傷であれば通常は胸部および骨盤、頸椎3方向の撮影のみが撮影対象となりますが、次の診療へと移行する際の課題として残る重要な項目は全脊椎・脊髄損傷のクリアランスです。必要に応じて実施されるこれらの撮影ですが、撮影条件として大きな負荷を要求される腰椎側面撮影も含まれ、患者の体型によっては移動型エックス線装置では十分な画質が得られにくい状況にあります。この撮影も、据置型エックス線装置を用いることにより十分診断が可能な画像を安定して撮影することが可能となります。
一方、ボケ像の識別限界を0.3mm[1] としますと横隔膜はおよそ10 mm/秒で移動することから呼吸停止の協力を得られない患者の場合、胸部および腹部の撮影は33msec.以下で撮影することが望ましいことになります。胸部の撮影(60kV)で必要なmAs値を3としますと240 mA、13msec.で移動型エックス線装置であってもその要件は満たします。腹部(80kV)の場合、必要なmAs値を20としますと移動型エックス線装置では180 mA、111msec.ですが、大出力の据置型エックス線装置ですと600 mA、33msec.となり求める基準を満たすことになります。
救急のエックス線撮影は、患者の協力が得られないことから再撮影などの不要な被ばくが生じる可能性をご理解いただけるかと思いますが、初期の診療で疾患を見逃すことが予後を左右したり、二次損傷を生じることがあることから、大出力エックス線装置を用いた短時間撮影が望ましいことは議論の余地がありません。十分な被ばくに対する対策を講じ、日常に被ばくを回避する意識を持ち続けることが必要と感じます。
回答3(国立保健医療科学院 山口一郎)
【医療放射線管理がめざすもの】
医療放射線管理がめざすものは、安全で良質な放射線診療の提供に他なりません。
ガイドラインやルールはその目的のために設けるものです。従って、法令適用においては単に現行法令の規定に反していないかどうかを検討するだけでなく、科学的根拠に基づくより有用なルール整備が必要かどうかを検証することも欠かせません。また、放射線安全に関わる行政の確認は、複数の施設を規制対象としているために、ある程度共通の基準に従うものの、個別性を重視し丁寧になされている実態にあります。このように、施設の特性を考慮した放射線安全への取り組みも求められます。
では、本題について平成17年度の厚生労働科学研究での検討[i] をもとに法令適用上の問題点と放射線診療上のあるべき姿から見た課題の解決の方向性を考えてみたいと思います。
【エックス線装置の使用場所に関する現行の規定】
エックス線装置はエックス線診療室で使用することが原則とされています(医療法施行規則第30条の4)。また、エックス線診療室には、放射線診療に関係のない機器をおいてはならないとされています(医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています))。この規定は、放射線診療専用の室で行うことを定めているものであり、その趣旨は、放射線安全の確保であると考えられます。
ただし、特別な場合は、エックス線装置は、エックス線診療室以外(例えば初療室)でも移動して使うことができます(医療法施行規則第30条の14)。この規定により、診療上必要がある場合に、放射線防護上の要件を満たしていれば、初療室において移動型の装置を用いたエックス線検査が行えることになっています。
【救命救急部の初療室での放射線診療の法令適用上扱い】
救命救急診療における放射線診療の提供方法としては、以下の3つのパターンが考えられます。
A) 初療室をX線診療室としてX線装置を設置する
(1) 放射線診療のみを行いベッドは一つ
(2) 放射線診療以外も行うなどそれ以外の想定
B) 初療室でのポータブル装置を用いた放射線診療
これらについて、法令適用上の問題を記します。
A) 初療室で放射線診療のみを行いベッドは一つであれば、法令適用の問題はないと考えられます。ただし、それ以外の想定では現行の通知と齟齬が生じます。通知では、放射線診療室での放射線診療に関係のない器具の設置や複数の患者の診療を行うことを禁じているからです。このため、これらの規定には反することになります。従って、安全な診療の確保の観点から問題があると考えられる場合には、使用前検査で不合格とすべきであり、医療機関への立入検査でそのような事実が確認された場合には医療法第24条の施設の使用制限命令等などの対象になり得ると考えられます。
B) 医療法施行規則第30条の14(使用場所の制限)の範囲内であれば、法令適用上の齟齬は来さないはずです。ただし、この場合は、あくまでも特別な使用になります。日常的に行われるのであれば、電離則との整合性も課題になり得えるでしょう。
【救急救命施設の初療室に天井走行型エックス線装置の想定される利点】
天井付近の空間を利用するので、診療の邪魔にならず、また、ポータブルX線装置にはない様々な利点があるため[2] 診療のパフォーマンスが上がることが想定されています。
天井走行型エックス線装置の方が大容量なので短時間撮影ができることにより画像の質はよくなります。ただし、もしかしたら現状のポータブルX線装置を用いた検査でも十分な情報が得られているのかもしれません。
【救急救命施設の初療室に天井走行型エックス線装置の想定される欠点】
装置の出力が大きいので患者の線量が大きくなります。残念なことに線量は把握され
ていないようですが、管電圧や実効稼働負荷の増加によりS値は従来のポータブルX線装置での検査に比べ倍半分程度になっています。このため、情報量の増加が線量増加の不利益を上回ることの検証も求められます。
また、装置の出力が大きいので不適切に扱うと放射線診療従事者の線量を多くする可能性があります。
【救急救命施設の初療室に天井走行型エックス線装置を設置した医療機関の実態】
初療室での検査件数は全く増加していないとされます。明文化されたガイドラインはないものの、初療室での検査の適応は変わらないとされます。このため無駄な検査をなされていないとされています。
防護はポータブルよりも徹底しているとされています。ただし、放射線診療従事の被ばく線量は他の医療機関よりも若干多いかもしれません。もっとも、職員にとっては線量増加の不利益よりもよい仕事への達成感が上回っているとされます。ただし、場のモニタリングはなされておらず個人モニタリングでは方向特性が極めて大きいために線量を過小評価していることが否定できません。
一方、外傷領域の救急救命診療では脊椎損傷のクリアランスが予後改善に重要です。
このため、画質の向上や検査の質の向上により、他の医療機関よりもこれらの患者の予後を改善しているかもしれません。坂下氏によるとその有益性は明らかとのことですので、そのような装置を設けていない救急救命センターはその機能を十分に発揮していないと考えられるのかもしれません。
【救急救命診療における放射線診療の課題】
救急救命診療が扱う疾患を診断できるための装置の最低スペックが必ずしも明らかされていません。とりわけ、照射法の選択がクリテイカルになる頸椎・胸椎移行部の撮影,胸骨側面撮影,股関節軸写撮影などについて必要な性能を検証すべきではないでしょうか。
また、ポータブルX線装置を用いた検査の適応について医療機関内の各診療科間でも十分なコンセンサスが得られているようには見受けられません。現行のJIS等ではポータブルX線装置と天井を移動する天井走行型の据置型X線装置で出力の制限での規定に差異はなく、単に市販されている装置の出力が異なっているに過ぎません。ポータブルX線装置はその診療目的に応じて様々に工夫されているものが販売されていますが救急救命診療に特化したものは見あたらないようです。
天井走行X線装置を用いない場合であっても、相当量の放射線診療がポータブルX線装置で行われています。小野らの報告によるとNICUに入院するELBWI-a児での平均ポータブルX線撮影回数は26回であるとされます[ii] 。放射線診療従事者の防護は概ねよくなされていると思われますが、患者を保持する必要があり、散乱体から至近距離であったり、患者を透過しないビーム内に体の一部が入ったりすることも考えられます。しかし、その場合であってもデジタル化された画像では保存時にトリミングするために看護師等に手指の電離放射線曝露状況が十分にフィードバックされていないことも危惧されます。
いずれにしても、放射線診療設備は救急救命診療にとっても重要です。事実、2006年1月にオープンした東海大学附属病院の高度救急救命センターでは、救急救命部と画像診断部を隣接させるだけでなく、救急救命部内にX線CT,血管造影、MRIが行える室をそれぞれ設けています。しかし、救急救命施設での放射線診療設備についての施設設計のガイドラインは存在していないようです。
【諸外国の状況】
救急救命施設の初療室に天井走行型X線装置を備えることを推奨している教科書は見あたりません。
一方、カナダのBritish Columbia Centre for Disease Controlは、2005年7月19日付で、複数の患者を扱い得る救急室での天井走行式のX線管を使う場合のデザインと配置についてのガイドラインを発行しています。このガイドライン発行の経緯は、救急室のポータブル装置を天井走行に置き換えたいという医療現場からの要望があったからとあり、救急の外傷患者のケアにおいて移動型装置を用いない場合に限り適用するとされています。このガイドラインではコントロール・ブースを設け、壁、床、天井に適切なシールドを設け、事前に、安全評価し、照射時に必要があればスタッフは防護衣を着用することとされています。この通知は、その必要があり我が国での規制を見直すのであれば、参考になると思われます[iii]。
【医療現場で今後望まれる対応】
・救急救命施設の初療室でハイスペックな側面撮影が有効かどうかを明らかにする。
・天井走行式のエックス線装置の導入が合理的になりうる医療機関がありうるかどうかを明らかにする。
・救急救命での放射線診療の品質管理や安全確保法を確立する。
救急医療での画像診断、防護に限らず規制との不整合については、
・何が課題か?
・どうして、問題が発生しているのか?
・それは検討に値する課題なのか(解決した場合の利益が十分に大きく、また、解決のための負担は相対的に小さいか?)
・問題を解決するには、どのような手法が考えられるのか?
などを明らかにすることが求められます。
[1] 医用放射線辞典,共立出版株式会社,1994
[2] 例えばCアームだとカセット保持や患者をおこしてのカセット交換の必要がない。また、ベッド周辺の医療機器が装置進入の障害になりにくい。
[i] 平成17年度厚生労働省科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業「医療放射線分野における法令整備等含めた管理体制に関する研究」(主任研究者:油野民雄)分担研究「医療機関における医療法施行規則との乖離点の整理及び医療法施行規則解釈の研究」課題:初療室でのエックス線装置の使用に関する規制整備のあり方についての検討報告書(分担研究者:山口 一郎).2006
[ii] K.Ono, K.Akahane, M.Hada, T.Mitarai, Y.Kato, M.Kai,T.Kusama. Frequency of X-ray Examinations of Neonates Classified According to Their Birth Weight in NICU. IRPA-10, P-17-13, 2000
[iii]British Columbia Centre for Disease Control. A Radiation Issue Note #16: Emergency Room Use of Ceiling Mounted X-ray Tubes. 2005
出典
日本放射線公衆安全学会.医療放射線管理についてのQ&A 救急処置室への据付型X線装置の設置について.日本放射線技師会雑誌 53(4),369-374(2006).
撤去例
国保旭 中央病院
五十嵐 隆元, (4)救急診療における放射線防護の在り方(分科会合同シンポジウム「救急検査のクオリティーを考える-救急撮影専門技師に求められるもの-」), 放射線撮影分科会誌, 2008, 51 巻, p. 61-63
初療室での天井走行型エックス線装置
日本救急撮影技師認定機構
済生会横浜市東部病院 救命救急センター
大阪府立泉州救命救急センター
国立病院機構水戸医療センター
初療室での透視型エックス線装置の設置例
さいたま市立病院
大阪府立急性期・総合医療センター高度救命救急センター
救急医学会総会でHybrid Emergency Roomを紹介
Hybrid Emergency Room IVR-CTを核とした新たな救急初期診療の提案
Hybrid Emergency Room設立にむけた 診療放射線技師としての運用効果
スリットビームを使った装置
IAEA
3.70. In many emergency departments, ceiling suspended X ray equipment provides a versatile environment for performing rapid trauma radiography. Appropriate occupational radiation protection can be afforded through the following:
(a) Lead aprons should be worn by staff members who need to be adjacent to the patient being exposed.
(b) The primary beam should be directed away from staff and other patients whenever possible.
(c) Staff should keep as far away as possible from the patient during exposure, whilst still maintaining good visual supervision of the patient.
(d) Where available, mobile shields should be used.
(e) Any pregnant staff member (other than radiology staff) should be asked by the medical radiation technologist to leave the vicinity during exposure.
(f) Verbal warning of imminent exposure should be given.
3.278.
Particular consideration should be given to persons in the radiology facility who are not undergoing a radiological procedure, but are in the vicinity when mobile radiography is being performed in their ward or area, or when fixed radiography is being performed in an open area, such as in an emergency department. In these cases, a combination of distance, placement of mobile shielding and careful control of the X ray beam direction should ensure that appropriate public radiation protection is being afforded.
医療事故
救急外来の患者のエックス線撮影を行う際、患者を取り違えて実施し他の患者のエックス線画像で異常なしと診断されたが、後日骨折があったことが判明した事例
放射線診療室の管理
現行の通知
放射線診療室において、放射線診療と無関係な機器を設置し、放射線診療に関係のない診療を行うこと、当該放射線診療室の診療と無関係な放射線診療装置等の操作する場所を設けること及び放射線診療室を一般の機器又は物品の保管場所として使用することは認められないこと。
IAEA SSG-46
The work area should be kept tidy and free from articles not required for work. A monitoring and cleaning programme should be established to ensure minimal spread of contamination. Cleaning and decontamination can be simplified by covering benches and drip trays with disposable material such as plastic backed absorbent paper.