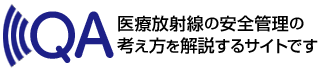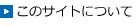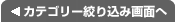No.126 健康診断の結果の記録の引き渡し機関
電離則に基づく健康診断の結果の記録の引き渡し機関はありますか?
電離則第57条(健康診断の結果の記録)で電離放射線健康診断の結果に基づき個人表作成してこれを30年間保存することになっています。
この条文では、医療機関が、5年間保存した後、厚生労働大臣の指定した機関に引き渡すことが出る旨の規定がありますが、この「厚生労働大臣が指定した機関」は現在存在するのでしょうか?
電離則の規定
健康診断の結果の記録
第五十七条 事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
指定された機関
財団法人放射線影響協会が電離放射線障害防止規則に基づく指定記録保存機関として指定されています。
指定記録保存機関の指定について
(平成21年12月1日)
(基安労発1201第1号)
(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
(契印省略)
標記について、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)、第57条及び第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)の規定により、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第98条第1項の指定記録保存機関として財団法人放射線影響協会を指定したので、別紙の事項について了知するとともに、関係事業者への周知等に遺憾なきを期されたい。
なお、指定記録保存機関への通知を別添のとおり添付する。
(別紙)
電離放射線障害防止規則に基づく放射線業務従事者等の線量の記録等の引渡し機関の指定について
1 制度の概要
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)の規定により、事業者は、以下の記録については、30年間保存する必要があるが、5年間保存した後、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡したときの保存を免除している。
(1) 外部被ばく線量、内部被ばく線量の記録
電離則第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)
(2) 電離放射線健康診断個人票(様式第1号)
電離則第57条
また、電離則第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)において事業を廃止するときは、事業者は、上記の記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すこととしている。
上記の指定は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)第96条第1項により、記録の保存業務を行おうとする者の申請により行うこととなっており、今般、その指定を受けるために、財団法人放射線影響協会から申請がなされ、登録省令第97条の指定基準等に適合することから指定したものである。
2 指定記録保存機関
指定記録保存機関の名称等は、次に掲げるとおりである。
(1) 名称 財団法人放射線影響協会
(2) 所在地 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
(3) 問合せ先 財団法人放射線影響協会放射線業務従事者中央登録センター
(4) 問合せ先の電話番号 03(5295)1790
URL:http://www.rea.or.jp/
3 業務
指定記録保存機関の主な業務は、次に掲げるとおりである。
(1) 事業者から引き渡された記録について、有料で保存すること。
(2) 事業者から引き渡された記録について、当該事業者又は当該記録に係る者からの照会及びその回答を行うこと。
(別添)
厚生労働省発基安1201第1号
指定記録保存機関通知書
財団法人放射線影響協会理事長 青木芳朗 殿
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)、第57条及び第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)の規定により、貴協会を労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第98条第1項の指定記録保存機関として下記のとおり指定したので通知する。
記
指定年月日
平成21年12月1日
名称
財団法人放射線影響協会
事務所の所在地
東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
平成21年12月1日
厚生労働大臣 長妻昭
放射性同位元素等の規制に関する法律
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
三 第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
人事院規則
第26条の2関係
2 特別健康管理手帳の様式、申請手続等必要な事項は、次のとおりとする。
(4) 各省各庁の長は、特別健康管理手帳の交付を受ける者が、長期的に適切な健康管理を行えるように、離職後の健康診断の受診勧奨その他必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。
人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)
(健康管理の記録)
第二十五条 各省各庁の長は、健康診断又は面接指導の結果(第二十二条の四第一項の検査の結果にあつては、同条第三項の同意を得て提供を受けたものに限る。)、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、人事院の定めるところにより、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 前項の記録は、職員が各省各庁の長を異にして異動した場合には、異動後の所属の各省各庁の長に移管するものとする。
3 各省各庁の長は、第一項の記録をその職員の離職した日から起算して五年間保存しなければならない。ただし、次の各号に掲げる業務に従事したことのある職員に係る記録については、当該職員の離職した日から起算して当該各号に定める期間保存するものとする。
一 別表第二第一号に掲げる業務のうち、石綿に係るもの 四十年
二 別表第二第一号に掲げる業務のうち、別表第二の二第二号1から44までに掲げる物質に係るもの 三十年
三 別表第二第三号に掲げる業務 七年
四 別表第三第二号に掲げる業務 三十年
別表第三 特別定期健康診断を必要とする業務(第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条関係)
一 別表第二第一号から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる業務
二 放射線に被ばくするおそれのある業務
三 せん孔、タイプ、筆耕、速記等による手指、肩、頸等に障害をうけるおそれのある業務
四 理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師等の業務で摩擦、屈伸等により障害をおこすおそれのあるもの
五 患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
六 深夜作業を必要とする業務
七 自動車等の運転を行う業務
八 調理、配ぜん等給食のため食品を取り扱う業務
九 計器監視、精密工作等を行う業務
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
(記録等)
第二十四条 各省各庁の長は、次に掲げるものについて記録を作成しなければならない。
一 第五条の規定による職員の線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
二 第十九条第二項第一号の措置を講じられた職員の身体の汚染の状態
三 緊急作業に従事した職員及び第二十二条の規定により医師の診察又は処置を受けた職員の実効線量及び等価線量又は汚染の状態
四 放射線業務に従事した職員の作業内容等
五 前条第一項から第三項までの規定による測定の結果
人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間)
規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の記録の文書等 離職した日 三十年
第二十一条各項の報告の文書等 取得の日 五年
第二十四条第一項第四号又は第五号の記録の文書等 作成の日 五年
第十一条第二項の記録の文書等 作成の日 三年
第十二条の届出の文書等 取得の日 三年
第二十七条第二項の報告の文書等 取得の日 報告に係る規程の効力が失われる日までの期間
離職後の健康管理対策
有害な業務に従事していた職員のうち、離職の後、特別健康管理手帳の交付要件に昨年10月以降該当することとなった者について、交付申請が適切に行われていることを確認する。
過去の経緯
砂屋敷 忠.医療における放射線関連の記録・帳票を価値あるものに
離職(退職)時の対応
基発 1027第4号 令和2年10月27日厚生労働省労働基準局長.電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について
なお、第9条第3項において、事業者は放射線業務従事者に同条第2項各号に掲げる線量を遅滞なく知らせなければならないこととされているが、事業場を離職する放射線業務従事者に対しては、当該離職する日までの同項各号に掲げる線量を知らせなければならないこと
記録の保存期間
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)
(記録の保存)
第七条 指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。
施行規則
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年文部科学省令第十三号)の施行に伴い、並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第二十条第四項第八号、第二十二条第二項第四号及び第二十六条第一項第六号の規定に基づき、記録の引渡し機関に関する省令を次のように定める。
線量測定
第二十条 法第二十条第一項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。
七 第二号から第五号の三までの記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、当該記録の対象者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
八 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
第二号から第五号の三までの記録
二 外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。
三 内部被ばくによる線量の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録すること。
四 前項の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあつては、次の事項について記録すること。
五 第二号から前号までの測定結果から、原子力規制委員会の定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。
五の二 前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量(前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
五の三 前号の規定は、第五号の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。
健康診断
第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
三 第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
四 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置
第二十六条 (許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置)
法第二十八条第一項に規定する許可取消使用者等が同項の規定により講じなければならない措置(以下この条において「廃止措置」という。)は、次の各号に定めるところによる。ただし、法第二十八条第七項に規定する従前の届出販売業者又は届出賃貸業者に係る許可取消使用者等(以下この条においてそれぞれ「販売廃止等業者」又は「賃貸廃止等業者」という。)については第六号及び第九号の規定を、同項に規定する従前の表示付認証機器届出使用者に係る許可取消使用者等(以下この条及び次条において「表示付認証機器廃止等使用者」という。)については第六号から第九号までの規定を適用しない。一 その所有する放射性同位元素を輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。
六 第二十条第一項から第三項までの規定(同条第一項第四号イからハまでの規定を除く。)による測定を行い、これらの測定の結果について記録すること。この場合において、同条第一項の測定(同項第四号ニの測定を除く。)については、第三号に規定する汚染の除去の前及び後に行うこと。
放射線影響協会による説明
記録の保存
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました
一元管理の困難さ
保存する機関での対応の課題
費用負担
1977 年の原子力登録管理制度発足後、放射線障害防止法(以下「RI 規制法」)の適用を受けるRI 等事業所を対象とした制度についても逐次拡大することとされていた。科学技術庁は、放影協に 1980 年度から 1984 年度の間、制度のあり方について調査・研究を委託した。その中で放影協にオフィスコンピュータとソフトウェアを整備し、1984 年 10 月に RI 等事業所における被ばく線量登録管理制度を発足させた。当初は、大学や医療機関等も制度の対象とすることを想定し、関係機関への説明会等を行ったが、費用負担の関係で理解が得られず、一部の法人と非破壊検査関係事業所等でスタートした。