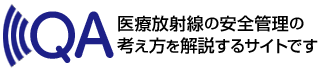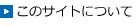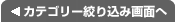No.178 GDやOSLなどを使った積算測定とサーベイメータによる線量率測定の比較
どちらの方法が優れていますか?
空間分解能
・手間を掛けるとどちらも分解能は上げられる。
・線量率測定では、複数人で行うと、その日の内に、ある程度、空間分解能が高い測定が行える。隙間も手間を掛けるとそれなりの感度でチェックはできる。
シールドの経時的変化
・ドアの閉まり具合で外側の線量が変わるとすると、線量率測定では、日常の線量を測定することが不可能。
・積算線量計だと設置する場所を工夫すると、一定期間中にドアのシールドが不十分で放射線が漏えいしていないかどうか、ある程度確認できる。
感度
・実効稼働負荷が大きい施設では線量率測定では検出限界が線量限度を担保できないことがある(ただし、最近、富士電機システムから診断領域のX線などを対象にした(10 keVから1.5MeVの光子に対してエネルギー特性が±25%以内でエネルギー特性の補正が不要)敷地境界の線量限度を担保するためのシンチレーションサーベイメータが発売されています。他社のシンチレーションサーベイメータでもエネルギー特性などを考慮すると原理的には線量限度を担保する測定が可能でしょう)。
どうしても隙間のシールド能力を確認したいのであれば、徳島大学のサイクロトロン施設での金箔での測定のアイデアを真似て、薄い素子を貼り付けておけば確認できそうです(TLシートやOSL)。
原理的には、エックス線装置から放出されるエネルギーを抑えておくと、そこから一定の距離の線量がある程度以下であることも科学的には示せるでしょう。
あるいは何らかの係数を考えて、フィルタを外すなど、サイクロトロンでのダンプターゲットを用いた漏えい線量測定と逆の発想も考えられるかもしれません。
また、我が国ではほとんど行われていませんが、壁の健全性評価という視点では、NCRP No. 147で示されているような線源を使った検査も考えられそうです(同様の言及例)。
いずれにしても、室外に滞在している人がある一定以上曝露していないことを示せればよいのであり、測定のコストはなるべく小さくするのがよいのではないでしょうか。
線源を用いた遮へいテストの言及例
個人線量測定協議会
参考:理研横浜研究所の多田順一郎先生からのコメント
管理区域境界の線量を最小検出感度の鈍い測定器で測定しようとすれば、この話のようになることは当然です。だからと言って、医療機関が大容量の加圧電離箱など用意できるはずもありませんから、ガラス線量計なりルクセルバッジなりを月単位の期間定置して積分値を測定するか、線源の近くの測定器がNDを示さない場所で測定して(スカイシャインや空気中の減弱などあまり気にせず)敷地境界にスケールして評価する方法をとるべきでしょう。
医療装置を痛めるような管理測定は本末転倒です。