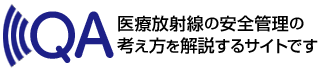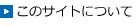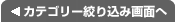No. 331 一時的に立ち入る者の放射線管理
年に数回、照射中のエックス線診療室に立ち入る職員でも個人モニタリングは必要ですか?
管理区域への立入
事業主は必要のないものを管理区域に立ち入らせてはなりません(電離則第3条)。
立ち入らせるとするとそれは業務上必要ということなります。
管理区域に立入る労働者
管理区域に立ち入らせる労働者は、「放射線業務従事者」か「管理区域に一時的に立ち入る労働者」のいずれかに区分されます。
基発第1号.電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について.昭和64年1月1日
線量モニタリング
このうち、放射線業務を行う労働者は、「放射線業務従事者」になります。
いずれにしても、線量の測定が必要です(電離則第8条)。
計算での評価
ただし、「管理区域に一時的に立ち入る労働者」では計算で確認することなどが認められている場合があります(外部被ばくによる実効線量が計算で求められ0.1 mSvを超えないか、放射線業務従事者と行動を共にし、過去の実績から外部被ばくによる実効線量が明らかに0.1 mSvを超えない場合)。
ただし、その場合であっても、立入と線量に関して記録し、1年間保存することが望ましいとされています(電離放射線障害防止規則の解説)。
一方、医療法施行規則では、実効線量が1週間につき100マイクロシーベルトを超える恐れのある場合は、線量の測定を行う必要があることとしています。
RI規制法での評価期間
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正及びこれに対する意見募集の結果について
JSRTの意見
線量計を装着するかどうかの判断を行う場合、100 マイクロSv の考え方を明確にする必要がある。
例えば、1回の入室での線量なのか、1日での線量なのか、その対象期間も明確でない。
規制側ではどのように考えているのか明確にしていただきたい。
原子力規制庁の考え方
一時立入りの期間は、許可届出使用者等が「一時的な立入り」として判断して、管理区域への立入りを認める期間になります。
一時的な立入りとして、管理区域に複数回入域する場合(例えば午前と午後に一回ずつ入域する場合等)には、それらの入域による外部被ばくによる線量を合算して評価し、一時的に立ち入る者の管理区域内における外部被ばく線量が実効線量について100 マイクロ・シーベルトを超えるおそれの有無により測定の要否について判断する必要があります。
関連質問
Q.年に数回、照射中のエックス線診療室に立ち入る職員でも健康診断は必要ですか?
放射線業務に常時従事する職員で管理区域に立ち入るものに対しては、事業主は、健康診断を行わなくてはなりません(電離則第56条)。
なお、常時従事するとは、頻度にかかわらず、反復継続することとされています。
Q.実際に立ち入っていなくても、今後、放射線業務を反復継続することを計画している場合も対象ですか?
予定している場合も対象になるとされています。
反復継続性
行政の見解例
「自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)」(平成29年7月28日観観産第173号)に関する参考資料
取引の反復継続性
業として営むとは、営利の意思を持って、反復継続して取引を行うことをいいます。
「5「住居」の意義」における反復・継続性
判例
裁判員経験者意見交換会議事録
宅地建物取引業者のした法律事務の取扱は、商法五〇三条により商行為となるとしても、それが一回かぎりであり、かつ、反復の意思をもつてされたものでないときは、弁護士法七二条に触れない。
宅地建物取引業法(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)一二条一項にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法二条二号所定の行為をなすことをいう。
放射線測定結果の記録の保管
放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関の指定基準等を定める省令案等に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
Q.臨時で放射線業務につかせる労働者にも特別な教育(電離則第52条の5)は必要ですか?
A.常用のみならず、臨時、アルバイトなどの短期間の被雇用者についても必要です(電離放射線障害防止規則の解説)。
労働時間は告示で定められています。
教育なしに業務につかせることの理解は得られないのではないでしょうか。
Q.放射線安全にコストがかかるので、労働者の放射線安全を簡素化してもよいですか?
A.コストかかるという理由は違法性阻却要因として認められません。法令上の義務を果たせない事業主はその業務を行う資格がないと考えられます。
関連記事
関連した取り組み
日本放射線公衆安全学会
放射線管理区域における一時作業者の放射線安全に関するガイドラインの提案.日本放射線公衆安全学会雑誌,11,3-10,2014
管理区域の一時的解除(照射中には立ち入らない場合)
要望例
日本放射線安全管理学会
検討の経過
放射線安全規制検討会
規制整備後の適用例
KEK
原子力規制庁. 放射線安全規制研究戦略的推進事業
原子力規制庁 放射線安全規制研究推進事業 放射線安全規制研究「放射線業務従事者」としての「指定」の在り方に関する検討 ―原子力施設等と医療施設の比較―
放射線看護学会
放射線診療(業務)従事者の指定に関するガイドライン-看護職者-
関連記事
患者への安全説明について議論されている例
第1回放射性同位元素等規制法に係る審査ガイド等の整備に関する意見聴取
実施が困難との訴えが医療機関側から寄せられていますが、安全に関する情報は放射線治療病室に入院する患者にも提供されているのではないでしょうか。
照射されない場合の扱いの議論
放射線管理の手間を考え、管理区域への一時立入を控えるように推奨している例
CT 検査室の前の廊下は管理区域にしてないと思うので、患者受け渡しは検査室の扉までということは徹底しておきましょう。中に入ると管理区域立ち入りになるので、病棟スタッフ等が気軽に管理区域内で手伝ってしまうことがないように、留意する必要があります。
医療安全の視点での検討も求められると思われます。
IAEAのSSG-46では、以下のような配慮を求めています。
3.54.Other radiology facility workers, such as ward nurses, imaging staff who work exclusively with imaging modalities without ionizing radiation (ultrasound or magnetic resonance imaging (MRI)), patient porters, orderlies, assistants, cleaners and other service support personnel, for whom radiation sources are not required by, or directly related to, their work, are required to have the same level of protection as members of the public, as established in para. 3.78 of GSR Part 3 [3]. Consequently, the recommendations provided in paras 3.277–3.280 are also applicable in respect of such workers. Rules should be established for these workers, especially with regard to access to controlled areas and supervised areas.
リニアック室への患者さんの送迎も想定されている例
第1回放射性同位元素等規制法に係る審査ガイド等の整備に関する意見聴取
○谷氏 日本放射線技術学会の谷です。
7ページですけども、【用語の定義等】というところで、取扱等業務というところがあります。放射線業務従事者の定義に係るところだと思うんですけども、この中の例示の中で、その次のページの中で、「同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄のほか、放射線発生装置の使用云々と点検、修理、管理等の業務をいう。」というふうに、はっきりと例示させていただいていて、非常にありがたいなと思うんですけども、我々御承知のとおり要求案ですとチーム医療といいまして、医師、看護師、クラークさん、事務方も含めていろんな方々が仕事している中で、今までどこの勉強会でもグレーになっていたのが看護師さんは従事者なのかどうですかというようなことがよく聞かれるんですけども、これはもうこのとおり理解しておいてよろしいでしょうか。であれば看護師さんは業務従事者、入れてもいいんですけども、入れなくても問題ないということで理解はよろしいですか。
職種ではなく業務性によるとの回答例
○鶴園安全管理調査官 ここのところは、どういう肩書きの人であればなるかどうかという議論ではなくて、要するにこの取扱等業務の定義のところからしますと、法令のところからしますと、少なくとも業務性はないといけませんでして、あとはここで書いてあるような付随する業務だとか、こういったものをやるような人であれば一応なりますので、どういう肩書きやどういう職業の人だから、それありきでなるとか、ならないという言い方はなかなか難しいです。
放射線業務従事者で管理区域への立入が一時的な場合のみの場合
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則での用語の定義
八 放射線業務従事者
放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であつて、管理区域に立ち入るもの
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則での健康診断
第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
一 放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
この規定では一時的にしか管理区域に立ち入らない放射線業務従事者がいるという想定になっている。
放射線診療業務従事者として扱う必要の有無の判断に関して頻度によるとしている職能団体の例
経緯(昭和33年3月31日)
第4節 放射線障害者の発見のための措置等
(放射線障害者の発見のための措置)
第15条 使用者及び販売業者が、法第23条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。
一 使用施設、詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者(一時的に立ち入る者を除く。)に対し、健康診断を行うこと。
日本アイソトープ協会
No.1 放射線発生装置のメンテナンス業者を受け入れるときの手続きを教えてください。
用語
保守点検業務を業者に委託している場合に保守点検を行う労働者は放射線診療従事者かどうか
医政発0323第21号(令和5年3月23日)
なお、エックス線装置等の保守点検業務を業者に委託している場合、保守点検を実施する者の当該業務による職業被ばくの管理は病院等の管理者ではなく労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく業務受託業者の義務であることから、放射線診療従事者等とはみなさないものであること。
一義的な責任の所在からの整理がなされていますが、IAEA GSR part3では以下のようになっています(shall cooperate)。
Requirement 23: Cooperation between employers and registrants and licensees
Employers and registrants and licensees shall cooperate to the extent necessary for compliance by all responsible parties with the requirements for protection and safety.
日本アイソトープ協会放射線安全取扱部会
No.1 放射線発生装置のメンテナンス業者を受け入れるときの手続きを教えてください。
(2)被ばくのおそれがない場合
No.72 管理区域に立ち入る者を一時立入り者とする場合は具体的にどんな時ですか。
業務の種類や被ばくのおそれの有無にかかわらず、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い又はこれに付随する業務(取扱等業務)のために管理区域に立ち入る者は放射線業務従事者として管理する必要があります。
○谷氏 そういうことですね。提携しているサービスマンにしてもそうなんですけども、
サービスマンをどうするかという形もいろいろと議論されていて、これにのっとれば必ず
業務従事者として扱うということになるんですよね。
○鶴園安全管理調査官 そういうことです。
放射性同位元素等規制法に係る審査ガイド等の整備に関する意見聴取 議事録