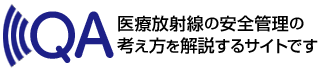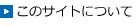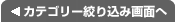No. 374 Ra-223を用いる場合のα線サーベイメータの配置
No. 374 Ra-223を用いる場合にα線サーベイメータを必ず備える必要がありますか?
必ずしも必要はありません。
関係学会等によるマニュアル
塩化ラジウム(Ra-223)注射液を用いる内用療法の適正使用マニュアル
8.2.1 アルファ線測定による Ra-223 の検出
Ra-223の使用に当たって、空間線量率、表面汚染検査、空気中濃度、排気・排水中濃度測定などの通常の放射線管理でアルファ線を測定対象とすることはあまりないが、表面汚染検査の際に、ベータ線測定に加えてアルファ線測定を活用すると有利なこともある。例えば、ZnS(Ag)シンチレーションサーベイメータを用いてアルファ線を測定対象にする場合と、GMサーベイメータを用いて主としてベータ線を測定対象とする場合を比較すると、GMサーベイメータのバックグラウンド計数率が 50~100cpm(2 インチφGM管の場合)であるのに対して、ZnS(Ag)シンチレーションサーベイメータのバックグラウンド計数率は 1cpm程度と低いために汚染の検出が容易で、低い検出限界値での検査が可能となる。さらに施設で使用するアルファ線放出核種がRa-223に限定されるなら、得られた計数は全てRa-223由来のものとみなすことができる。
このように表面汚染検査においてアルファ線を測定対象とすることに確かに利点はあるものの、自己吸収について十分に注意しなければならない。8.1 でも触れたように、アルファ線の物質に対する透過力が極端に弱いため、表面汚染源からアルファ線がどのくらい放出されているか(線源効率)を十分に把握しておかなければならない。表面汚染源の状態によってはアルファ線の自己吸収が大きく、ほとんど汚染源表面からは放出されないこともある。また、汚染層が薄くても汚染源の表面が他の物質で覆われていることもある。このようにアルファ線は一般的に表面から放出される割合が低く、過少評価をする結果になるので、注意が必要である。また、汚染源表面からはアルファ線が放出されていても、汚染源と検出部の距離が離れていると、その間の空気層での吸収が大きくなり、これも過少評価に結び付くこととなる。アルファ線測定の場合は入射窓面と汚染源表面との距離を 5mm 程度に保って測定しなければならず、特に汚染放射能を定量するときには適切な治具を用いるなどして距離を一定にしなければならない。一方、空気による吸収を低くするために汚染源に近づけ過ぎると、検出部を汚染させたり、入射窓を破損する結果となるので注意しなければならない。このようにアルファ線を測定するときには、検出部と線源との位置関係(ジオメトリ)だけでなく、その間におけるアルファ線の吸収を十分に把握して、測定ごとに異なる計数効率を評価しておかなければならない。汚染源の形状、形態がいつも一定であることはなく、測定の度に計数効率を求めることは、通常の汚染検査では不可能なことである。したがって、アルファ線を測定対象としたアルファ線放出核種の表面汚染検査には前述のような利点も確かにあるが、医療現場での通常の表面汚染検査には適切な方法とは言い難く、GMサーベイメータなどを用いたベータ線測定が有効な検査となる。