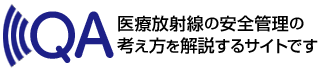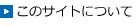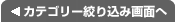No. 409 放射線の労働災害(労災)認定事例
放射線の労働災害(労災)認定事例について教えて下さい。
電離放射線障害の業務上外に関する検討会
電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について
電離放射線障害の労災認定
皮膚がんでの労災事例
事例
業務上疾病の労災補償状況調査報告書(平成14年10月)
岡﨑 龍史, 日本における放射線に関わる法令, Journal of UOEH, 2013, 35 巻, Special_Issue 号, p. 85-89, 公開日 2013/10/10, Online ISSN 2187-2864, Print ISSN 0387-821X
医療機関で放射線を扱うことのリスクは大きいですか?
労災認定基準
歴史的経緯
石井 義脩, 電離放射線障害の労災認定, 保健物理, 1994, 29 巻, 1 号, p. 4-6
諸澄邦彦.電離放射線防止規則
補償
NCRP
Lens of Eye Guidance- Next Steps A Stakeholder Workshop on Implementation and Research
Topic 3 Wider Implications of Implementing the Revised Limit
– long term impact on working activities; – changes in Health surveillance; – more claims for compensation
事後的な線量評価法
A proposed method for retrospective eye dose assessments for the purposes of resolving cataract compensation claims.
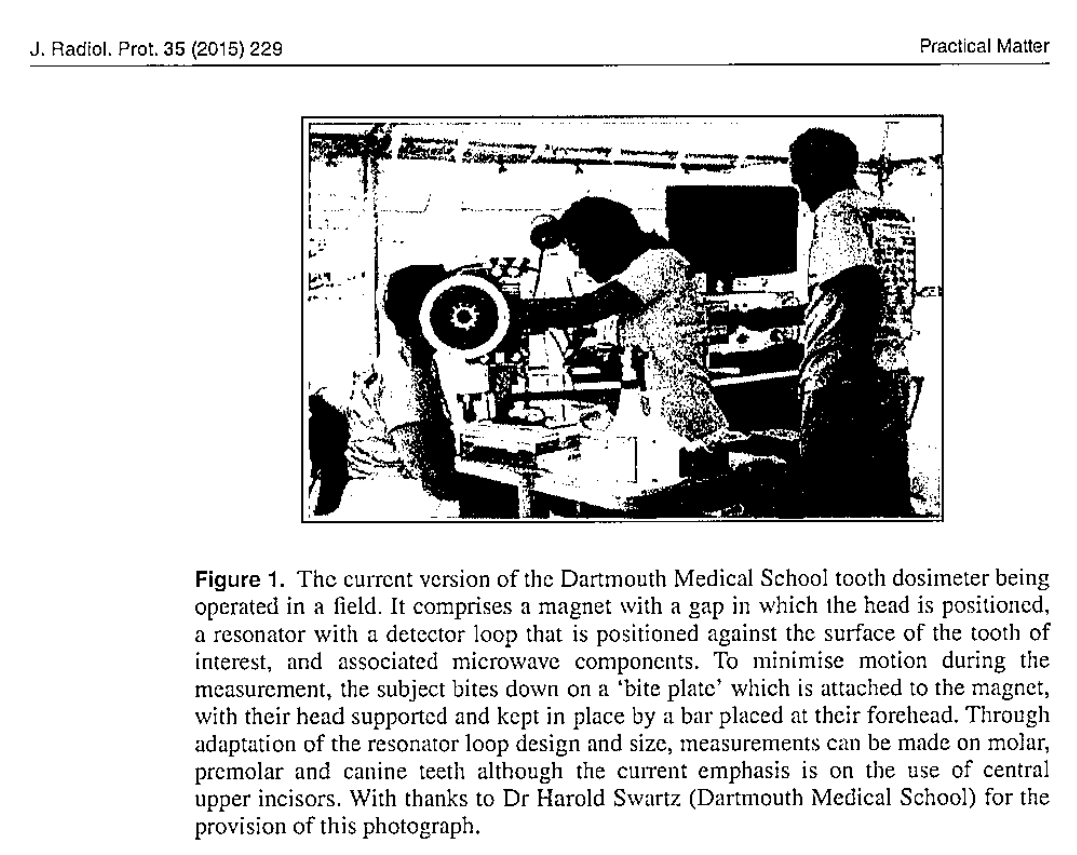
VA Programs For Veterans Exposed To Radiation
IRPA
lens of eye, dose monitoring and protection
Report of IRPA task group on the impact of the eye lens dose limits
Q16. Are there any circumstances in which you foresee that the introduction of new limits for the workers might lead to more claims for compensation?
IRPA guideline protocol for eye dose monitoring and eye protection of workers
厚生労働省
1-5 労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられるのでしょうか。
放射線被ばくによる疾病についての労災保険制度のお知らせ
監督
イギリスの労働基準監督官制度
英国における労働安全衛生関係法令の概要
教育
VR教材体験会
労災体験×安全衛生教育×VR
Kakimoto A, Fujise D, Hasegawa S, Okuda Y, Ohta Y, Tani R, et al. Virtual reality-based training for radiopharmaceutical administration: development and educational effectiveness. Anwar MS, editor. PLoS One. 2025;20:e0321101.
リソース
白内障
電離放射線に係る疾病の認定基準について(昭和51年11月8日基発810号)
6 白内障
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(1) 相当量の電離放射線を眼に被ばくした事実があること。
(2) 被ばく開始後少なくとも1年を超える期間を経た後に発生した疾病であること。
(3) 水晶体混濁による視力障害を伴う白内障であること。
第2 電離放射線に係る疾病の認定について
6 白内障について
(1) 本文記の第2の6の(1)の「相当量」とは,次の線量をいう。
イ 3カ月以内の期間における被ばくの場合おおむね200レム又はこれを超える線量
ロ 3カ月超える期間における被ばくの場合おおむね500レム又はこれを超える線量
(2) 電離放射線による白内障は,被ばく後長期間を経た後に発生するので,「老人性白内障」との鑑別が困難な場合が多い。したがって,被ばく線量を十分には握のうえ業務起因性を判断することが必要である。
(3) 慢性的に電離放射線に被ばくしている場合には,眼の被ばく線量が測定されていることは稀である。
全身にほぼ均等に被ばくしていると判断される場合には,下記第3の1の(1)の個人モニタリングによる測定値に基づいて算出された集積線量をもって眼の被ばく線量として差し支えない。全身に均等に被ばくしていない場合で眼の被ばく線量が個人モニタリングによる測定値に基づいて算出された集積線量より多いと判断されるときは,その集積線量,作業状況,作業環境,安全防護の状況等(以下「作業状況等」という。)を総合的に検討して被ばく線量を推定する必要がある。
眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会
実情を把握して、それに沿って対応していこうとする丁寧な議論がなされていました。
個人線量モニタリングの実態に関して
出典:第5回 「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」議事録
日本整形外科学会
○中村日本整形外科学会理事(三上参考人代理) これはもう取り組まないと駄目だと思いますけれども、ちょっと私としましては、ガラスバッジはだいたい全員着けていますので、それ以上に手術場で着けていないのかどうかというのは、そこの問題はあろうかもしれませんけれど、通常はもう着けているものだと思っていました。この数字には非常にびっくりしておりますので、学会の方でまず検討いたします。
日本循環器学会
○池田参考人 循環器も56%という数字を見ましてびっくりしたのですが、多くは大学病院とか総合病院の大きいところはですね、フィルムバッジを着けないと仕事できないようなシステムになっているのですが、残念ながら今回ご依頼したところに民間病院のところがあったのですけれども、そういったところではもしかしたらこういった実態なのかなと改めて思いましたので、学会として取り組むと同時に、今回のこの新しい取り組みはですね、潜在的に隠れている被ばく量の多い人を洗い出すにはいい取り組みかなと思いました。
日本診療放射線技師会
○富田参集者 我々、先ほどもちょっと申しましたように診療放射線技師がほとんどの病院で放射線の医療現場にいると思って間違いないと思っています。従いまして、我々の業務、もちろん撮影だけではなくて危機管理、それから線量評価というところも現場では一番詳しいというふうに自分たちは、医療の中では思っておりますので、我々もこのフィルムバッジ、ガラスバッジの装着状況を見させていただいて非常にびっくりしたところもございまして、同じように我々診療放射線技師の中でもこの辺の調査も含めて今後ちょっと取り組んでいきたいと思いました。
日本消化器病学会
○持田参考人 バッジ装着率が43%と低率で驚きましたが、消化器領域は23施設での検討で、かなり信頼性がある数値と思います。日本消化器病学会に持ち帰って、対策することを提案します。消化器領域では、放射線を用いた手技は、主として内視鏡室で行われるといった特殊性があり、放射線技師の管理が行き届いていない可能性があります。日本消化器病学会とともに日本消化器内視鏡学会にも連絡し、両学会で情報を共有して会員に啓発していく必要があると考えます。