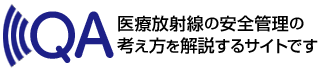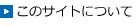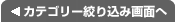No.166 放射線障害の発生するおそれのある場所の測定
医療法施行規則第30条の22(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)では、エックス線診療室や診療用高エネルギー放射線発生装置使用室等室内が放射線障害が発生するおそれのある場所とされています。
これらの室内でも放射線の量を測らなくてはならないでしょうか?
電離放射線防止規則
作業環境測定を行うべき作業場
第五十三条 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
線量当量率等
第五十四条 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、六月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定器の種類、型式及び性能
四 測定箇所
五 測定条件
六 測定結果
七 測定を実施した者の氏名
八 測定結果に基づいて実施した措置の概要
2 前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
3 第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。
4 事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。
通知の考え方
医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)では放射線障害の発生するおそれのある場所に関して、測定や計算による算定について説明されています。
計算と測定による評価は、放射線安全上、重要です。
測定の意義
計算による評価が適切かどうか、それが変化していないかが測定で確認できます。
室内での測定では、その意義がどの程度あるかが実務上のポイントになるでしょう。
室内の線量やその分布の把握の意義
室内に立ち入ることで放射線にさらされる場合
血管系IVR,非血管系IVR,密封小線源治療,RI検査,消化管検査等では、各使用室内で放射線診療従事者が放射線にさらされます。
また、放射線治療では、装置から照射される放射線に直接さらされることはありませんが、生成された放射化物からの放射線にさらされます。
室内の線量分布を把握する意義
これらの診療内容は多様ですが、装置の導入時に線量分布を測定しておけば,放射線防護の参考になります。
室内の線量分布の経年変化は出力などに依存
装置等の出力又は,放射能強度の点検を行っていれば,線源条件に変化はありません。
線源条件に変化がなく、装置を含むシールドが劣化・変化しなければ、線量分布に変化はありません。
使用実態に応じた放射線防護の重要性
特にIVRでは、直接線による被ばくを避けるだけではなく、患者からの散乱線からの曝露を低減するような防護が重要です。
日々の放射線診療の内容に応じ,直接線被ばくを少なくする,透視時間の短縮,有効な防護具の活用等が求められます。
事後的な管理
各使用室は管理区域内にあります。管理区域に立入る者は,必ず個人被ばく線量測定器で測定し管理されているので,個人測定により事後的にモニタリングされています。
しかし、それだけでは十分ではなく、事前安全評価による防護の最適化が重要です。
業界団体による指針
JIS
JISZ4716:X線診療室の漏えいX線量の測定方法
細沼 宏安.JIS Z 4716 X 線診療室の漏えいX 線量の測定方法 制定の経緯とその内容
以下未整理
④建屋の経年変化等による防護機能の劣化のないことを確認する
放射線障害の発生し得る場所では,建屋の防護基準と線量限度が定められているので,建屋の老朽化や破損による防護機能の劣化等がないことを確認する必要があります。そのため,6カ月に一度,使用室の隔壁の外側,管理区域境界等の線量測定を行い建屋の防護機能を確認することは有効と考えられます。
医療法で放射線障害の発生するおそれの場所の測定義務が課せられ,これに相当する関係法令を見てみると次のとおりです。
障害防止法(現RI規制法)では「放射線障害のおそれのある場所」としています,測定場所は次のとおりです。
(抜粋)
(測定)
第二十条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
施行規則第20条
放射線の量
イ 使用施設
ロ 廃棄物詰替施設
ハ 貯蔵施設
ニ 廃棄物貯蔵施設
ホ 廃棄施設
ヘ 管理区域の境界
ト 事業所等内において人が居住する区域
チ 事業所等の境界
電離則では「管理区域に該当する部分」という表現を用いています。
(抜粋)
(作業環境測定を行うべき作業場)
第53条 令第21条第6号 の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
(1) 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
(2) 放射性物質取扱作業室
(3) 令別表第2第7号に掲げる業務を行う作業場
(線量当量率等の測定等)
第54条 事業者は、前条第1号の管理区域について、1月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3. 7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内)ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
4 事業者は、第1項の測定又は第2項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。
老朽化への対応の議論例
線量の基準
放射線障害防止法(現RI規制法)
放射線障害防止法施行規則
(使用施設の基準)
第十四条の七 法第六条第一号 の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
三 使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて原子力規制委員会が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年第5号)
(遮蔽物に係る線量限度)
第十条 規則第十四条の七第一項第三号(規則第十四条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する同号イに掲げる線量に係る線量限度については、実効線量が一週間につき一ミリシーベルトとする。
測定の信頼性
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正及びこれに対する意見募集の結果等について ―放射線測定の信頼性確保の義務化―
質問:本法律とは別の医療法、労働安全衛生法との連携は今後どうなるのでしょうか?
回答:なお、御意見にある「医療法、労働安全衛生法との連携」については、厚生労働省をはじめとした関係省庁にも本改正に関して情報提供をしていますが、今後の対応については承知していません。
第71回原子力規制委員会
資料2 放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイドの一部改正(測定の信頼性確保関係)
JIRA
漏洩線量測定
X線診療室の管理区域漏洩線量測定マニュアル Instruction manual for measurement of X-ray leakage from controlled areas
関連記事
『おそれのある』
有害物の有害性等に関する掲示内容における「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例を掲載しています。
省略規定
作業環境測定基準
第九条 電離放射線障害防止規則第五十三条第二号、第二号の二又は第三号に掲げる作業場における空気中の放射性物質の濃度の測定は、次の方法によらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる放射性物質の状態に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる試料採取方法(表)
二 次に掲げるいずれかの分析方法
イ 次に掲げる分析方法(アルファ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はアルファ線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(1)に掲げる分析方法による分析を、ベータ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はベータ線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(2)に掲げる分析方法による分析を、ガンマ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はガンマ線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(3)に掲げる分析方法による分析を、それぞれ省略することができる。)
(1) 全アルファ放射能計測方法又はアルファ線スペクトル分析方法
(2) 全ベータ放射能計測方法又はベータ線スペクトル分析方法
(3) 全ガンマ放射能計測方法又はガンマ線スペクトル分析方法
IAEA SSG-46
3.101. Workplace monitoring in areas around each item of medical radiological equipment in the radiology facility, when it is being operated, should be carried out when:
(a) The room and shielding construction has been completed, regardless of whether it is a new construction or a renovation, and before the room is first used clinically;
(b) New or substantially refurbished equipment is commissioned (both direct and indirect radiation such as leakage and scatter radiation should be measured);
(c) New software for the medical radiological equipment is installed or there is a significant upgrade;
(d) New techniques are introduced;
(e) Servicing of the medical radiological equipment has been performed, which could have an impact on the radiation delivered.