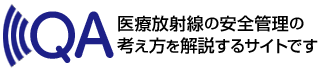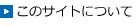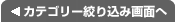No.14 管理区域境界等の線量測定
管理区域境界の漏えい線量測定を、6ヶ月を越えない期間で1回行っています。
使用測定器は、電離箱サーベイメータ(アロカ製 ICS−321)です。
エックス線撮影装置等は積算線量、透視装置は線量率で測定しています。
積算線量測定は、照射回数3回の積算値から1回当たりの平均値を求めています。
質問の続き
この測定値に3月あたりの実効稼動負荷を考慮して管理区域境界の線量限度である1.3mSv/3Mを超えないか確認しています。
線量率測定は、照射時間10秒以上の数値を測定値としています。
積算線量測定値が検出限界を超えなかったときは、測定器の検出限界である0.3μSvから1回あたりの照射での漏えい線量が0.1μSv以下であると仮定し3月あたりの実効稼動負荷をかけて評価しています。
しかし、積算線量の評価で3月あたりの実効稼動負荷が多い場合、管理区域境界の線量限度である1.3mSv/3Mを超える場合がありました。
例)CT装置 1人あたり照射回数20回・1日撮影人数10人・週6日稼動・13週 の場合
20[n/person]×10[person/day]×6[day/week]×13[week]=15,600回照射(3月あたり)
測定平均値(3回照射) 0.1μSv × 15,600回 =1,560 μSv > 1.3mSv/3月間
この場合、1測定点の測定回数を増やすことによって、1回あたりの平均値を少なくすることで管理区域の線量限度をクリアすることが出来ますが、照射回数が多くなることで装置等に負担が多くなることからどういった評価方法がよいのか思案中です。
病室、事業所境界の線量限度等の評価方法についてもどういった評価方法がよいのか教えてください。
回答
測定値が検出限界を超えなかったということは、
3月間の線量の大きさが
検出限界の値(mSv/mAs)×3月間の実効稼働負荷(mAs/3M)÷測定時の実効稼働負荷(mAs)
を超えないと考えてよいでしょう。
測定時間や回数を長くすると検出限界を小さくできるでしょう。
そのための手間がかかりすぎるようであれば、積算型の線量計を用いるのも一つの方法でしょう。
評価法はいくつかありますが、それぞれ、利点と欠点を比較して総合的に考えるのがよいでしょう。
漏洩線量測定事業
岩手八幡平歯科医師会
名古屋市歯科医師会協同組合
医療監視に関わるX線測定器について
令和7年度名古屋市歯科医師会医療監視資料
対馬市歯科医師会
一般社団法人久留米歯科医師会
11.サーベイメータ(エックス線漏えい計測機器)の貸出しと指導
医療法施行規則で義務づけられた放射線量測定(6か月を超えない期間ごとに1回)
実施のため、会員の歯科診療所に対しサーベイメータの貸出しと指導を行った。
鹿児島県医師協同組合
公益社団法人鹿児島県診療放射線技師会
長岡市医師会
医療法人伊藤歯科医院
徳島市医師共同組合
一般社団法人 群馬県診療放射線技師会
群馬県診療放射線技師会放射線管理部では、X線を使用されている御施設様に対する、漏えい放射線量測定事業を提供しております。
宮城県放射線技師会
大分県放射線技師会
高知県診療放射線技師会
測定の間隔を減らしてはどうかとの意見例
日本画像医療システム工業会
令和4年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての関係府省からの第2次回答について
令和4年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての最終的な調整結果について
医療法に基づくエックス線診療室等の漏洩線量定期測定義務の見直し
令和4年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 厚生労働省 第2次回答
記述の矛盾点
『エックス線診療室等から外部に放射線が漏洩する可能性はなく、』とありますが、室外への放射線の漏えいは容易に検出できることがあります。
配慮すべき点
医療分野では線量限度を超えるような曝露をする労働者が多数いると考えられることから、作業環境モニタリングの側面も重視すべきだと思います。
公衆の線量限度担保の観点
米国
§ 20.1302 Compliance with dose limits for individual members of the public.
(a) The licensee shall make or cause to be made, as appropriate, surveys of radiation levels in unrestricted and controlled areas and radioactive materials in effluents released to unrestricted and controlled areas to demonstrate compliance with the dose limits for individual members of the public in § 20.1301.
(b) A licensee shall show compliance with the annual dose limit in § 20.1301 by—
(1) Demonstrating by measurement or calculation that the total effective dose equivalent to the individual likely to receive the highest dose from the licensed operation does not exceed the annual dose limit; or
(2) Demonstrating that—
(i) The annual average concentrations of radioactive material released in gaseous and liquid effluents at the boundary of the unrestricted area do not exceed the values specified in table 2 of appendix B to part 20; and
(ii) If an individual were continuously present in an unrestricted area, the dose from external sources would not exceed 0.002 rem (0.02 mSv) in an hour and 0.05 rem (0.5 mSv) in a year.
(c) Upon approval from the Commission, the licensee may adjust the effluent concentration values in appendix B to part 20, table 2, for members of the public, to take into account the actual physical and chemical characteristics of the effluents (e.g., aerosol size distribution, solubility, density, radioactive decay equilibrium, chemical form).
[56 FR 23398, May 21, 1991; 56 FR 61352, Dec. 3, 1991, as amended at 57 FR 57878, Dec. 8, 1992; 60 FR 20185, Apr. 25, 1995]