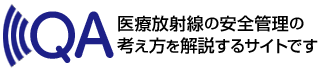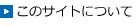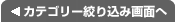No.11 X線CT室からの漏えい線量
照射野の大きいX線CT装置を設置したところ、鉛当量2mmの鉛ガラスの外側で照射時に14μSv/hの放射線の漏えいがありました。
計算では散乱体から評価点までの距離が2.25mしかないために鉛ガラス外側での散乱線などに由来した漏えい線が3月間で0.6mSv程度になっています。
遮へいの追加が必要ですか?
X線診療室としての防護
1日の照射時間が1時間であるとしても、1週間での線量は14μSv/h×1h/d×5(or7)d/w≒0.1mSv/wに過ぎません。従って、X線診療室の防護基準は満足しています。
また、1時間当たりの漏えい線量率は14 μSv/h×1/8≒2 μSv/hであることから、医療法施行規則第30条の23【記帳】の適用は免除されます。
ただし、線量限度を満足していても、ALARAの原則が適用されるので、
(1)合理的に低減できているか?
(2)関係者の理解は得られているか?
を考慮する必要があります。
敷地境界や医療機関内の人が居住する区域の境界の線量限度の担保
その場所が敷地境界や医療機関内の人が居住する区域であるとすると、
・3月間の線量は、0.1 mSv/w×13 w/3M=1.3 mSv/3M
となるので、その線量限度が担保できません。
このため、管理区域境界の線量限度が担保されているかどうかの確認が必要です。
ビル診療所のX線CTで診療所境界での線量限度の担保が厳しいとして、一日の検査数を実際によりも少ない設定にするのは不適切です。
関連FAQ
Q.X線診療室の外側で100 μSv/d以上の漏えいがあった場合に、遮へいの追加は必要ないのですか?
A.1日の漏えい線量が100 μSv/dであれば、1週間の線量が1mSvを超えないのでX線診療室の防護基準は満たしています。
しかし、地方厚生局の中には、X線診療室の外側での漏えいを100 μSv/d未満とするよう行政指導している例があります。これは、X線診療室の外側の操作室を管理区域外と考えていることに基づいています。
このようにどこまでの漏えいを許容するかは、当事者の意向を考慮する必要があるでしょう。
単に放射線管理担当者が、この程度のリークはOKと判断するのではなく、労働者の合意を得ておくのがトラブル防止や職場の安全意識の醸成に有用でしょう。
また、わが国では、ビル内の医療機関で管理区域境界=敷地境界となりますが、距離が確保できないため、高出力のX線CT装置では線量限度を担保するのが困難になるという課題があります。線量限度を担保するために検査件数を適当に設定することは適切ではありません。このような課題に対応するために、平成21年度の厚労科研で合理的な評価方法を提案しています。
Q. 他のX線装置使用室では検出されないのに、多列化したX線CT装置使用室が検出されたのか疑問です。
A.同じ遮蔽体の厚みであれば、線量率測定では、多列化したX線CT装置で最も漏えい線量が検出しやすいと考えられます。その理由は単位時間当たりに照射する光子数が多いからです。
もっとも血管透視装置でも注意深く測定すると観察窓の外側で照射中に線量率が上昇することが確認出来るでしょう。
それに対して検診車では壁が薄いので、漏えい線量の検出は容易です。
Q.X線室から放射線が漏れてはいけないのではないですか?
A.線量限度を超えない量であれば、漏えいすることは法令上許容されます。
ただし、ALARAの原則に従う必要があります。
あなたはどう思われますか?
医療放射線防護連絡協議会の医療放射線管理講習会の参加者では、この事例では、より遮へいを追加すべきという意見が多数となっていました。
解説
本院の研修では医療機関の見学時にX線CT室からの漏えい線量をデモしています。
ある医療監視員との医療機関への立入時のやりとり例
監視員
「管理区域の線量限度は1.3 mSv/3月間です。
労働時間は、3月間で160520時間ですから勤務時間中の線量率は、
1.3mSv/3月間÷160520時間=8.132.5 μSv/hを超えてはいけません。
これ以上の線量率であれば管理区域の線量を超えています。
X線CT室の外側の線量率は14 μSv/hとなっていますから、線量限度を超えています。
診療放射線技師長
X線CT装置の照射時間は1日8時間の労働時間内で10分間にもなりません。
サーベイメータは単位時間あたりの線量率を示すので、「/h」で表示されますが、数秒間の曝射が1時間続いた場合の値を表示しているだけです。
監視員
数秒の曝射でもそこに1時間いれば記録どおり14 μSvとなりますから、隣の診療科のスタッフが問題にしますよ。
診療放射線技師長
照射時間を考慮すると微々たる線量です。それに職員は納得しています。
監視員
サーベイメータは、その場の測定結果を示しています。
その場に1時間いたら10 μSv/hになるんじゃないですか?
その様に記載されていますよ。
職員本人が納得していても職員の家族からクレームが来たらどうするのですか?
診療放射線技師長
(心の中のつぶやき)「これ以上の会話は平行線だ・・・・」「医療監視員は必ず研修を受講してから業務にあたるようにして欲しい」
後日談
診療放射線技師長は188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)に沿った記録方法に変更し、
1日の照射時間が200秒であることから、
0.7[s/回転]×7[回転]×30[人/日]+53[s/一日あたりの品質管理照射]=200[s/d]
1日の漏えい線量は
10[μSv/h×200[s]≒0.8[μSv/d]
であり、3月間の漏えい線量は51[μSv/3月間]と記帳することにしたそうです。
後日談への突っ込み例(装置の高性能化や検査の高度化に対応したパラメータ設定となっていますか?)
品質管理照射が加味されているのは、賞賛です。現場では見たことありません。
しかし、0.7[s/回転]×7[回転]は適切だとは思えません。現在、頭部でも10回転以上の撮影が一般的ですし、3Dや3,4相造影となれば、10秒/人以上の撮影はざらにあります。
200秒を担保するには、30人/日はありえません。
参考読み物
小沢健一.暴走の死角.数学セミナー.6月号.1978
関連小咄
制限時速50キロのところで、スピード違反でつかまり
警察官に「時速80キロで走行していた」といわれ、そのときの言い訳が
「この道路で時速80キロで走るのは不可能です。1時間で30キロも走ることが出来ませんよ」