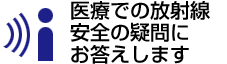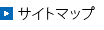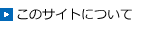X線CT検査は胸部X線検査に比べて放射線の量が100倍程度大きいので、放射線の影響が心配になるけど、検査を受けると本当にDNAは2本鎖切断するのですか?
DNA2本鎖切断を可視化することが可能になったから、研究で調べることができる。
どの程度の感度があるのですか?
人間のリンパ球でも3 mGyの線量で生じるDNA2本鎖切断が検出可能なようじゃ。線量と細胞内のDNA2本鎖切断の数が比例することも確認されておる。
X線CT検査だと、どの程度のDNA2本鎖切断が生じるのですか?
DLP(dose length product)が1,000 mGy・cmの場合は、照射直後に、一つの細胞あたり0.2カ所のDNA2本鎖切断が生じるとされておる。
DLPは、ある線量がどの程度の範囲に与えた(=X線ビームがどの程度の範囲を走査したか)を示すものでしたよね。DLPが1,000 mGy・cmというのは、実効線量だとどの程度ですか?
ICRP(国際放射線防護委員会)のpublication 102のTable A.2.にDLPから実効線量への換算係数が記載されておる。
検査の種類や年齢によって異なるが、成人の腹部・骨盤部だとDLPが1 mGy・cmあたり実効線量は0.015 mSvとされておる。
だとすると、実効線量で15 mSvですね。
このDNA2本鎖切断はきちんと修復されるのですか?
観察すると1日で修復されることが確認できる。
修復に要する時間はそれほど長くないということじゃ。
もっとも、DNA2本鎖切断が修復されても、放射線のリスクは無視できないことがある。修復でエラーがおきた場合には、健康影響が考えられるからじゃ。放射線診療従事者を長期間追跡した調査では、線量とともに染色体異常が増加しているという報告がある。
生体には放射線のダメージを修復する機能はあるけど、放射線検査では利益とリスクを比較する必要があると言うことだね。
この記事は、放射線総合医学研究所の島田義也先生から文献の紹介を受けて作成しました。
参考にした文献は、島田義也ら.医療被曝と発がんリスク.公衆衛生,73(12),922-926, 2009です。
第104回日本医学物理学会の市民公開講座で、千葉大学付属病院の加藤英幸さんが、自らの体験を話されました。彼は、それぞれの手技時(ステント留置術とX線CT検査)にガラス線量計を入れたチューブを上部消化管に留置し、線量分布も同時に把握し、それぞれの手技によるDNA2本鎖切断修復のパターンの違いを観察されていました。
IAEA
Radiation Effects Measurement in CT and Interventional Procedures
文献
In vivo formation and repair of DNA double-strand breaks after computed tomography examinations
DNA Double-Strand Breaks after Percutaneous Transluminal Angioplasty
Leukocyte DNA Damage after Multi–Detector Row CT: A Quantitative Biomarker of Low-Level Radiation Exposure
Effect of CT scan protocols on x-ray-induced DNA double-strand breaks in blood lymphocytes of patients undergoing coronary CTA
DNA double-strand breaks as potential indicators for the biological effects of ionising radiation exposure from cardiac CT and conventional coronary angiography: a randomised, controlled study.
Assessment of the Radiation Effects of Cardiac CT Angiography Using Protein and Genetic Biomarkers.
DNA damage seen in patients undergoing CT scanning
Leukocyte DNA damage after reduced and conventional absorbed radiation doses using 3rd generation dual-source CT technology
関連記事
関連研究
【研究成果】低線量放射線に対する感受性には個人差があることが判明 ―CT検査などの人体への軽微な影響が評価可能に―