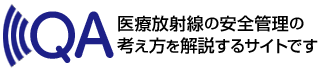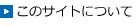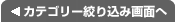No. 296 超短半減期核種の数量
超短半減期核種の数量は、どう設定するのがよいですか?
減衰を考慮して、平均存在数量を用いることが推奨されています。
平成12年10月23日 国際放射線防護委員会の勧告(ICRP Pub.60)の取り入れ等による放射線障害防止法関係法令の改正について(通知)
人が常時立ち入る場所の空気中の放射性同位元素の濃度
1 超短半減期の核種については、減衰を考慮した値の使用についても可能とする。
問題点
「人が常時立ち入る場所の空気中の放射性同位元素の濃度」以外については明示されていない。
原子力安全技術センター
放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル
4.1.12 超短半減期核種の数量
日本アイソトープ協会
18F-FDGを用いたPET診療における医療放射線管理の実践マニュアル
関連記事
FAQ
平均存在量を用いる評価は、使用時間中、継続して漏れているとの考え方が前提であるが、実際は使い始めに一気に漏れることが考えられるので、平均存在量を用いた安全評価は不適切ではないですか?
シナリオにより非安全側の評価となる場合
- 漏えい時の濃度推計で、時間が経過した後の濃度測定値から、漏えい時の濃度を推計する場合(空気中での拡散などの影響は補正したとの前提で)、実際は使用開始時に一気に漏れたにもかかわらず、継続して漏れていたと仮定すると、漏えい時の濃度を過小評価します。
Q.「漏えい時の濃度を過小評価します。」とあることは、過小評価しないためには減衰補正してはだめということになりませんか?
以下のようにする必要があるのではないでしょうか。
- 「漏えい時の濃度を過小評価」しないように恣意的に減衰補正しない。
- 「三月間の平均濃度」を評価するために、減衰補正を科学的に妥当な方法で適用する。
測定から濃度の換算が非安全側ではないことの説明方法
漏えい時の濃度推計で、時間が経過した後の濃度測定であるにも関わらず、持続的に漏えいした、あるいは測定直前に漏えいしたとすると非安全側になると思いますが、濃度推定した値が安全側であることを説明するにはどうすればよいですか?
- 漏えいが短時間に起こり、時間が経過してから測定したと仮定する(安全側ではあるが、この評価法で安全を担保するには過大なコストがかかる)
- 濃度限度を超えるような環境放出があった場合には、警報が発せられることや、濃度測定のログから、漏えいが短時間に起こり、時間が経過してから測定したのではないことが説明され、より合理的に評価する
平均存在量を用いた事前安全評価
- 漏えいの割合を仮定し、それでも線量限度が担保できるかどうかを確認します。
- ここでの漏えいの割合の想定は一定を仮定しています。
- 潜在的なリスクとして漏えい割合が時刻により変化すると考えられる場合には、その要素を加味する必要があるでしょう。
- 潜在的なリスクへの対応として何らかのアラームを設ける場合には、リスクレベルも考慮することが必要でしょう。
使用数量をどう考えるのがよいですか?
放射能は、単位時間あたりの壊変数で時刻によって変化しうる値です。使用はその時刻に関心対象空間に存在していることと考えられますので、安全評価では、その放射性物質がどのように供給されるのかなどを考え、評価時間中の積分量を考慮する必要があるでしょう。
米国のルールとの違い
N-13やO-15の空気中や排気中の濃度限度は日本と異なっていますか?
米国では、作業者が吸入する空気のDerived Air Concentration (DAC) は、4E-06 [µCi/ml](1.5E-01 [Bq/ml])とされ、排気の濃度限度は2E-08 [µCi/ml](7.4E-04)とされています。
日本ではそれぞれ2.0E-01 [Bq/ml]と7.0E-04[Bq/ml]とされており、ほぼ同じレベルとなっています。
SECY-07-0062 Final Rule: Requirements for Expanded Definition of Byproduct Material (RIN: 3150-AH84)
NRC Final Rule on Expanded Definition of Byproduct Material
EU
COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM of 5 December 2013
O-15の告示別表の扱い
告示別表第2の「排気中の濃度限度」(第5欄)は、一般公衆に対する各年齢層毎(3 ヵ月齢、l 歳、5 歳、1 0 歳、1 5 歳、成人)の吸入関数による線量係数及び成人に対する不活性ガス等による線量率係数を用いて、「外部被ばく及び内部被ばくの評価法に係る技術的指針」が示すところの、同一人が誕生してから7 0 歳(満7 0 歳の誕生日まで)になるまでの期間について、年平均1 mS v (実効線量)の被ばく線量に基づくものとして算出しています。
詳細の計算
詳細な計算については、当時の原研の報告書「ICRPの内部被ばく線量評価法に基づく空気中濃度等の試算」に記載されています。
O-15の化学形ごとに分けていない理由
その10ページ目にO-15の化学形ごとに分けていない理由と思われることが記載されています。
試算は当時のICRP Pub.68とPub.72に基づいて計算をしているのですが、その中にO-15がなかったようです。
それでもO-15のサブマージョンは当時の告示に掲載されていることから独自に計算したようです。
ICRPに記載がなかったにも関わらずO-15が当時の告示に掲載されていたのは、おそらく日本でO-15検査が行われていたことによると考えられます。
C-11が化学形ごとに分けられている理由
C-11についてはICRP68に掲載されているため化学形に場合分けして計算されたのではないかと思います。
サブマージョンを計算したのは外部被ばくの影響が大きい(外部被ばくが支配的とされる不活性ガス等である)ためだと考えられます(4ページ目に記載があります)。
ICRP 2007 年勧告の組織加重係数等への対応
その後、ICRP 2007 年勧告の組織加重係数等に基づいて、内部被ばく線量係数が計算し直され『ICRP 2007 年勧告の組織加重係数等に基づく内部被ばく線量係数』が出されていますが、この報告書でもO-15はサブマージョンしか計算されていません(この報告書の目的から)。
O-15は不活化ガス?
O-15の内部被ばくはこちらをご覧下さい。
関連記事
臨床的有用性
岡沢 秀彦, 工藤 崇.H215Oによる局所脳血流量の測定と臨床応用
平均存在数量の放射線管理での利用が合理的ではないとしている例
変更承認申請について
短半減期のPET 核種では遮蔽計算においては1 日最大使用数量の代わりに平均存在数量を使用することができます。平均存在数量は F-18(半減期)では 1 日最大使用数量の 30 % 程度となり、その他のもっと半減期の短い核種では更に小さな値になります。平均存在数量を使用することにより遮蔽計算に余裕を持たせることができますが、平均存在数量を空気中濃度や排気口濃度に使用することは合理的ではありません。そこで今回空気中濃度や排気口濃度に平均存在数量を使用しない条件での再検討を行い、変更承認申請を行いました。主な変更点は PET 核種について三月、年間の使用数量を減少するもので、1 日最大使用数量の変更はありません。PET 核種について使用回数が減ることになり、ご不便をおかけすることになります。この申請は平成 27 年 8 月 17 日に行い、平成 27 年 11 月 2 日に承認されました。
安全評価例
第135回総会放射線審議会
O-15の数量の考え方は明示的には示されていないようです。
関連記事
連続供給核種
連続供給核種においては、「一日最大使用数量」ではない概念を用いるのが良いのではないか。
このため、現在の法令の下では、検査において、変更許可の前提事項となっている一日最大使用数量について、確認することは必要である。
第4回放射性同位元素等規制法に係る審査ガイド等の整備に関する意見聴取
ログ解析での異常事象発見の取り組みの成果としてのセキュリティ対策への反映
学会でのセッション
第16回学術大会(保健物理学会合同開催・大分), 日本放射線安全管理学会誌, 2017, 16 巻, 2 号, p. 35-71
放射線安全管理の新しい試み【第1回 医療分野での新しい課題】 -事業所からの放射性物質の環境への放出の制御の課題など-