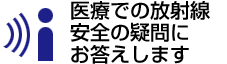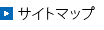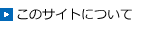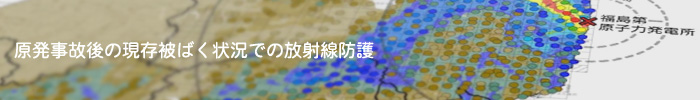原子力発電所事故後の現存被ばく状況での放射線防護のカテゴリーの記事は、保健福祉職員向け原子力災害後の放射線学習サイトに移行中です。
外部被ばくと内部被ばくの違い
外部被ばくと内部被ばくは何が違うのかな?
線源が体外にあるか体内にあるかじゃ。
線源を取り込むことのリスク
それだけ?
内部被ばくは体内に線源があるから危ないんじゃないかな?
電離エネルギーを受ける細胞からは、放射線が体内から飛んできたのか、体内から飛んできたのか区別できん。
長く続く被ばくと短時間の被ばく
内部被ばくは放射性物質を体内に取り込むので、被ばくし続けるからより危ないのじゃないかな?
外部被ばくも受け続ける場合があり、その場合には、線量を受け続けるかどうかの観点では違いはない。
本当に同じなの?
内部被ばくに特有なことはないのですか?α線は危険だと聞くけど…。
α線による曝露は、体外に線源があるとすると、細胞核にまで影響を与えることが困難じゃ。
重粒子線治療では高いエネルギーを用いておる。
α線を出す核種は体内に取り込むと危険だと言うことですね。
同じ電離エネルギーを与える場合でもα線は生体が応答しにくいように与えるので影響が大きいと考えられておる。
放射線防護上は、放射線加重係数はα線に対して20が与えられておる。
α線を放出する放射性核種を用いた放射線治療としてはRa-223を用いたものの臨床試験が開始されておる。この治療法は骨転移に対しても骨髄への影響を小さくできる特徴がある。そこでのデータからも生物学的効果比(RBE)が確認できるようになるじゃろ。
食品摂取による線量でPo-210の寄与が比較的大きいのも、それに関係しておる。
防護法
防護法ではどのような違いがありますか?
外部被ばくは、線源を減らすこと、線源から遠ざけること、シールドすること、線源に近づく時間を減らすことを組み合わせることになる。
内部被ばくは、放射性物質の取り込みを減らすことや取り込んだ放射性物質を減らすことを組み合わせることになる。
距離の逆二乗則ですね。でも、逆に距離が近いと線量がうんと大きくなるのではないかしらん。1/10の距離だと百倍になってしまう。1cmの距離に対して1µmまで近づくと108も増加してしまう。さらに、1nmに近づくと、そこから108も増加するということはすごいことになりそうだけど、これであっているのだろうか?
距離の逆二乗則は、距離によるフルエンスが球の半径と表面積の関係で示させることがもとになっておるが、微小空間でのエネルギー付与分布は、距離の逆二乗則には、もちろん従わない。
総合的に考えて(=対策がもたらす不利益も考慮して)、できる手段で有効なもので優先度の高いものを行うと言うことですね。
外部被ばくと内部被ばく時の生体内電子の飛跡シミュレーション
参考資料
ICRP 2007年基本勧告に基づく 線量評価用換算係数について
放射線防護で用いられる線量について
ICRP 2007 年勧告の組織加重係数等に基づく内部被ばく線量係数、濃度限度等の試算 (受託研究)