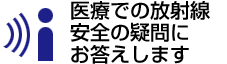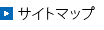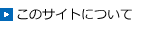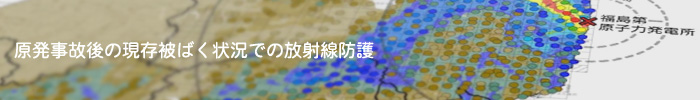原子力発電所事故後の現存被ばく状況での放射線防護のカテゴリーの記事は、保健福祉職員向け原子力災害後の放射線学習サイトに移行中です。
ICRP
Using the Latest Dose Coefficients: ICRP Data Viewer, IDEAplus, and TAURUS
ICRP, 2012. Compendium of Dose Coefficients based on ICRP Publication 60. ICRP Publication 119. Ann. ICRP 41(Suppl.).
| ICRP Publication 141 | Occupational Intakes of Radionuclides: Part 4 |
| ICRP Publication 137 | Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3 |
| ICRP Publication 134 | Occupational Intakes of Radionuclides: Part 2 |
| ICRP Publication 133 | The ICRP Computational Framework for Internal Dose Assessment for Reference Adults: Specific Absorbed Fractions |
| ICRP Publication 130 | Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1 |
解説資料
高橋 聖,吉澤 道夫.ICRP Publication 130「放射性核種の職業上の摂取(OIR)Part1」の概要と主な変更点
環境放射線モニタリングに関する指針
〔表I-1〕1 Bqを経口又は吸入摂取した場合の成人の実効線量係数(mSv/Bq)
| 核種 | 経口摂取 | 吸入摂取 |
|---|---|---|
| I-131 *1 | 1.6×10-5 | 1.5×10-5 |
| Cs-137 | 1.3×10-5 | 3.9×10-5 |
*1 ICRP Publication 66などのモデルを基に摂取されたヨウ素が体液中から甲状腺へ達する割合を0.2として計算した値である。
〔表I-2〕1 Bqの放射性ヨウ素を経口又は吸入摂取した場合の幼児及び乳児の実効線量係数*(mSv/Bq)
| 核種 | 経口摂取 | 吸入摂取 | ||
|---|---|---|---|---|
| 幼児 | 乳児 | 幼児 | 乳児 | |
| I-131 | 7.5×10-5 | 1.4×10-4 | 6.9×10-5 | 1.3×10-4 |
* 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(原子力安全委員会、平成13年3月)による。
〔表I-3〕1 Bqを経口又は吸入摂取した場合の成人、幼児及び乳児の甲状腺の等価線量に係る線量係数*(mSv/Bq)
| 核種 | 経口摂取 | 吸入摂取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人 | 幼児 | 乳児 | 成人 | 幼児 | 乳児 | |
| I-131 | 3.2×10-4 | 1.5×10-3 | 2.8×10-3 | 2.9×10-4 | 1.4×10-3 | 2.5×10-3 |
* 本表の値は、ICRP Publication 66などのモデルを基に摂取されたヨウ素が体液中から甲状腺へ達する割合を0.2、化学形を元素状として計算した値である。
IDEC/INDESによる経口摂取時の計算例
[Sv/Bq]
Sr-89
| 年齢層 | 実効線量率係数 |
|---|---|
| 0歳≦3月児<1歳 | 4.2E-08 |
| 1歳≦1歳児<3歳 | 1.8E-08 |
| 3歳≦5歳児<8歳 | 8.9E-09 |
| 8歳≦10歳児<13歳 | 5.8E-09 |
| 13歳≦15歳児<18歳 | 4.0E-09 |
| 18歳≦成人<70歳 | 2.6E-09 |
Sr-90
| 年齢層 | 実効線量率係数 |
|---|---|
| 0歳≦3月児<1歳 | 2.4E-07 |
| 1歳≦1歳児<3歳 | 7.2E-08 |
| 3歳≦5歳児<8歳 | 4.5E-08 |
| 8歳≦10歳児<13歳 | 5.8E-08 |
| 13歳≦15歳児<18歳 | 7.8E-08 |
| 18歳≦成人<70歳 | 2.8E-08 |
Cs-134
| 年齢層 | 実効線量率係数 | 甲状腺等価線量率係数 |
|---|---|---|
| 0歳≦3月児<1歳 | 3.0E-08 | 2.9E-08 |
| 1歳≦1歳児<3歳 | 1.6E-08 | 1.6E-08 |
| 3歳≦5歳児<8歳 | 1.3E-08 | 1.3E-08 |
| 8歳≦10歳児<13歳 | 1.4E-08 | 1.4E-08 |
| 13歳≦15歳児<18歳 | 1.9E-08 | 1.9E-08 |
| 18歳≦成人<70歳 | 1.9E-08 | 1.9E-08 |
Cs-137
| 年齢層 | 実効線量率係数 | 甲状腺等価線量率係数 |
|---|---|---|
| 0歳≦3月児<1歳 | 2.5E-08 | 2.2E-08 |
| 1歳≦1歳児<3歳 | 1.2E-08 | 1.1E-08 |
| 3歳≦5歳児<8歳 | 9.6E-09 | 9.0E-09 |
| 8歳≦10歳児<13歳 | 1.0E-08 | 9.7E-09 |
| 13歳≦15歳児<18歳 | 1.3E-08 | 1.3E-08 |
| 18歳≦成人<70歳 | 1.4E-08 | 1.3E-08 |
I-131
| 年齢層 | 実効線量率係数 | 甲状腺等価線量率係数 |
|---|---|---|
| 0歳≦3月児<1歳 | 2.0E-07 | 3.9E-06 |
| 1歳≦1歳児<3歳 | 1.8E-07 | 3.6E-06 |
| 3歳≦5歳児<8歳 | 1.0E-07 | 2.1E-06 |
| 8歳≦10歳児<13歳 | 5.2E-08 | 1.0E-06 |
| 13歳≦15歳児<18歳 | 3.4E-08 | 6.8E-07 |
| 18歳≦成人<70歳 | 2.2E-08 | 4.3E-07 |
IDECへの言及例
FAQ
線量換算係数のデータはどこから入手できますか?
ICRPのサイトからダウンロードできます。
Free Educational CD Downloads
子孫核種の扱い
The database includes results for all nuclides considered in ICRP Publications 68 and 72. Radiation decay data are taken from ICRP Publication 38. Many radionuclides decay to nuclides that are themselves radioactive, these are often termed radioactive daughters. The results given in the database take into account the ingrowth of daughters in all regions of the body following an intake of unit activity of the parent nuclide. They do not take into account any activity of daughter nuclides in the initial intake. This is in line with current and previous ICRP dose compendia (Publications 30, 68, 72).
線量換算係数の例
トリチウム
C-14
F-18
Fe-55
Sr-89
Sr-90
Ru-103
Sb-124
Sb-125
Te-125m
Te-129m
Te-132
I-131
I-132
I-133
I-135
Cs-134
Cs-136
Cs-137
Lu-177
Lu-177m
Po-210
Pb-211
At-211
Ra-223
Ra-224
Ra-226
Ac-225
Th-232
U-234
U-238
Pu-239
Am-241
セシウム137の経口摂取時の実効線量係数は、大人は1.3×10-5[mSv/Bq]とあるようですが、乳幼児や5歳か6歳の子供にも、同じ係数が適用されるのでしょうか。乳幼児は別の係数があるのでしょうか?
単位摂取放射性物質当たりの実効線量換算係数や甲状腺等価線量係数などは年齢などに依存します。
代謝に依存
早く排泄されると体内での崩壊数が減るので線量が小さくなります。
代謝パターンは吸入摂取と経口摂取で異なります。
体格に依存
線源臓器(放射性物質が取り込まれた臓器)と対象臓器の距離が短いと線量が大きくなります。
原子力発電所等周辺防災対策専門部会環境ワーキンググループ
飲食物摂取制限に関する指標について(平成10年3月6日)
乳児:2.1×10-5[mSv/Bq]
幼児(5歳):9.7×10-6[mSv/Bq]
ICRPが提示している年齢区分
3か月児:生後から12カ月まで
1歳児:1歳から2歳まで
5歳児:2歳から7歳まで
10歳児:7歳から12歳まで
15歳児:12歳から17歳まで
成人:17歳以上
代謝のパターン別の係数の違いを示した例
核種によってはある臓器で濃縮されるものがあると思います。このような核種はより危険なのでないでしょうか?
線量換算係数は臓器での濃縮のされやすさも考慮しています。
実効線量係数が国際放射線防護委員会(ICRP)によって示されていることはわかりましたが、この線量係数はどのような算出されるのかが知りたいです。もし実効線量係数を統計学的に扱えるのであれば、その平均値と分布(あるいは標準偏差)が教えていただけませんか?
実効線量換算係数は何で決定されますか?
その核種の核データ
半減期や放出される放射線の種類やエネルギー、放出割合
これらは、ある不確かさを持ちます。
その核種の代謝
線源となる臓器に存在する程度、線源臓器内での存在部位
これらは、ある不確かさを持ちます。
内部被ばく線量評価コードで条件を変えて計算すると、その大きさが評価できます。
線源臓器と標的臓器の関係
臓器や体格の大きさや元素組成、密度
防護量としての実効線量係数は標準人を対象にしています。
この標準人は性差のない仮想的なもの
これらは、ある不確かさを持ちえており、ICRP Publ.100にその議論があります。
実効線量係数の不確かさ
以上の不確かさが合成されうると考えられます。
原子力安全委員会の「飲食物摂取制限に関する指標について」と薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会報告とでは、用いている線量換算係数が異なっているのは何故ですか?
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会報告の線量換算係数
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会報告策定時点での国際放射線防護委員会の最新データは、Pub.72またはICRP CD-ROM1(Dose Coefficients: Workers and Members of the Public)であり、このデータを用いています。
原子力安全委員会の「飲食物摂取制限に関する指標について」(平成10年)の線量換算係数
ICRP Pub. 67で示された係数を基本的に用いています。
これらや防災指針との違い
ICRP Pub.67とICRP Pub.72の間には本質的な差異はなく、示されている係数に大きな違いはありません。
昭和55年に発行された原子力安全委員会「原子力発電所周辺の防災対策について」では、放射性ヨウ素の係数に関して、わが国では食事からの安定ヨウ素摂取量が大きく甲状腺への取り込み割合が小さい(成人でほぼ0.15であり(Tanakaら1979)、0.2で安全側設定になるとされる(吉沢ら1976))ことから、血液から甲状腺への移行割合を0.2としていますが、放射性ヨウ素以外では、ICRPの出版物で示された係数の誘導の前提となる代謝パラメータをそのまま用いています。
血中から甲状腺への移行割合のデフォルトは0.3であるので、この防災指針に示されている係数は、ICRPの線量係数より低くなります。
その程度はおおよそ、指針/ICRPで0.7程度となります。
線量換算係数は、いつまでに受ける線量を考慮しているのですか?
70歳に達するまでに受ける積算線量(預託実効線量)ですが、成人では摂取後50年間を想定しています。
このため、年齢が高いと過大評価することになります。
子供の場合は、例えば、8歳から13歳までの年齢区分は、10歳児の線量係数(←今後60年間の積算値)を用いるので、年齢区分の範囲で平均すれば,成人のような過大評価にはなりません。
線量換算係数では、年齢別の放射線感受性の違いが考慮されていますか?
いいえ、考慮されていません。
年齢別の放射線感受性の違いは、介入線量レベルの違いなどにより考慮することになります。
線量換算係数で年齢に違いが考慮されているのは、(1)体格、(2)代謝の違いです。
政府広報オンライン
ご存じですか?食品中の放射性物質の新しい基準値は、子どもたちの安全に特に配慮して定められています
外部被ばくと内部被ばく時の生体内電子の飛跡シミュレーション
ICRP Publ.72に出ているカリウム40の線量係数(6.2E-9 Sv/Bq)の値は、実効線量に換算する数値でしょうか?それとも、預託実効線量に換算する数値でしょうか?カリウムは生体内では平衡状態ですから、預託という概念は当てはまらないように思いますがいかがですか?
内部被ばくでの預託という概念は、取り込んだ放射性核種により、その後、受け続けるであろうと考えられるものを摂取時にまとめて評価するということを意味します。
この観点では、その物質が生体内で平衡状態に達しているかどうかは、預託という概念を使うかどうかとは関係がありません。
体内での挙動と平衡状態
取り込んだ物質が体の中で平衡状態にあるとすると、排泄が促進されることが考えられます。
カリウム40などの線量換算係数は、年代別に与えられていますが、それぞれ、標準的な代謝モデルを使い、線源臓器への集積の経時変化を想定し、そこでの総崩壊数が推計されます。一方、線源臓器から標的臓器に与えられる単位崩壊当たりのエネルギーを標準的な解剖条件で得て、線量が推計されています。
このように線量換算係数は、特定の代謝条件を仮定しているので、それに合わない条件では、線量を過小評価したり過大評価することになります。
カリウムをたくさん摂取しても線量増加は限定的
カリウム40は、体の中で平衡状態にあるために、多く摂取しても預託実効線量を増加させる影響が乏しいと考えられます。
体内に存在するK-40の量から、各臓器に与えられる単位時間あたりのエネルギーを計算し、そこから線量を求めたものは、預託実効線量と言えないと考えてよいでしょうか?
K-40は、体内で平衡状態にあると考えられるので、線源臓器での単位時間あたりの壊変数から、線量率を求めることができます。
臓器の中のKの量がわかれば、臓器に中に存在するK-40の量が推計できます。
毎秒あたりに壊変する数がわかると、単位壊変あたりのβ線の放出割合(89.3%)、β線の最大エネルギー(1.312 MeV、より厳密には単位壊変あたりに放出するβ線のエネルギー分布)、単位壊変あたりのγ線の放出割合(10.7%)、γ線のエネルギー(1.416 MeV)から、単位壊変あたりにK-40から供給されるエネルギー量が計算されます。
K-40から供給されるエネルギーのうち、標的臓器に付与される割合から、線源臓器での単位時間あたりの壊変数から、標的臓器に与えられる単位時間あたりのエネルギー[J/s]が求められ、それを標的臓器の質量[kg]で割ると、吸収線量率[J/kg/s=G/s]を求めることができます。
得られた線量率から評価期間を考慮すると線量が得られます。
こうして得られた線量は、体内に定常的に存在するK-40に由来するものであり、おっしゃるように「預託」という概念を用いていないと思われます。
慢性摂取では、時間の経過と共に代謝の仕方が変わってくると思いますが、そのことは考慮されていますか?
検討している例です。
慢性摂取による内部被ばく線量評価コードの開発
Isaksson M, Tondel M, Wålinder R, Rääf C. Absorbed dose rate coefficients for134Cs and137Cs with steady-state distribution in the human body:S-coefficients revisited. J Radiol Prot. 2021 Nov 24;41(4). doi: 10.1088/1361-6498/ac2ec4
空気中の放射性ヨウ素131を吸入することによる線量
1 Bq/m3の濃度の場合
| 年齢階級 | 実効線量換算係数[Sv/Bq] | 甲状腺等価線量換算係数[Sv/Bq] | 一日あたり呼吸量[m3/d] | 一日あたりの吸入による線量[µSv/d] |
|---|---|---|---|---|
| 0歳≦3月児<1歳 | 2.00E-07 | 3.90E-06 | 2.86 | 11 |
| 1歳≦1歳児<3歳 | 1.80E-07 | 3.60E-06 | 5.16 | 19 |
| 3歳≦5歳児<8歳 | 1.00E-07 | 2.10E-06 | 8.72 | 18 |
| 8歳≦10歳児<13歳 | 5.20E-08 | 1.00E-06 | 15.3 | 15 |
| 13歳≦15歳児<18歳 | 3.40E-08 | 6.80E-07 | 20.1 | 14 |
| 18歳≦成人<70歳 | 2.20E-08 | 4.30E-07 | 22.2 | 10 |
uncertainty
経緯の説明
稲葉 次郎.ICRP Publication 68とPublication 72の紹介
Compendium
ICRP Publication 119. Compendium of Dose Coefficients based on ICRP Publication 60
ツール例
ICRP2007年勧告に基づく内部被ばく線量評価コード
内部被ばく線量係数計算システムDSYS-GUI
慢性摂取による内部被ばく線量評価コードDSYS-Chronic
内部被ばく線量評価支援ソフトウェア MONDAL の開発
内部被ばく線量評価コードIMBA
内部被ばく線量評価コード FlexID