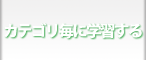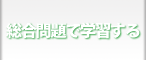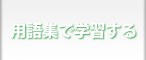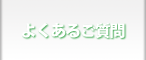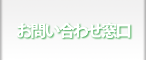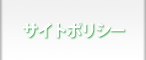|
||
問題公衆の線量限度(年間1ミリシーベルト)を超えた場合以下の文章は正しいですか? 参考資料等
基準の整理例現存被ばく状況での参考レベルのバンドの幅20mSvは現存被ばく状況での参考レベル設定範囲の上限とされています。 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書年間20ミリシーベルトは、より一層の線量低減を目指すためのスタートとされています
出典低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書 健康への影響とこれからの取組み ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について(平成 23 年 12 月 26 日 原子力災害対策本部)年間20ミリシーベルト以下は、避難指示解除の必須の要件原子力安全委員会は、本年8月4日に示した解除に関する考え方において、解除日以降年間20ミリシーベルト以下となることが確実であることを、避難指示を解除するための必須の要件であるとの考えを示した。 年間積算線量が20ミリシーベルト以下で「避難指示解除準備区域」に移行
新たな避難指示区域に関する基本的考え方と今後の課題に対する対応方針一律の取扱いとはせずに、段階的な解除も可能
出典ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について 帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方(原子力規制委員会)参考レベルは関係者で協議してそれぞれ設定すべきとされている国際放射線防護委員会(ICRP)は、緊急事態後の長期被ばく状況を含む状況(以下、「現存被ばく状況」という。)において汚染地域内に居住する人々の防護の最適化を計画するための参考レベル(これを上回る被ばくの発生を許す計画の策定は不適切であると判断され、それより下では防護の最適化を履行すべき線量又はリスクのレベル)は、長期的な目標として、年間1~20ミリシーベルトの線量域の下方部分から選択すべきであるとしている。過去の経験から、この目標は、長期の事故後では年間1ミリシーベルトが適切であるとしている。参考レベルは、地域の汚染状況に加えて、住民の社会生活、経済生活及び環境生活の持続可能性、並びに住民の健康など多くの相互に関連する要因のバランスを慎重に検討し、関係するステークホルダーの見解に基づいて、それぞれ設定すべきであるとしている。 第55回 原子力災害対策本部特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方(案) 出典帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方(原子力規制委員会) 関係資料平成 24 年 7 月 原子力災害対策本部 原子力被災者生活支援チーム避難指示区域の見直しにおける基準(年間 20mSv 基準)について 帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム(第 1 回会合)線量水準に関連した考え方 ( 原子力災害対策本部関係省庁説明資料(別紙1)) 異なった見解を持つ専門家が討論しているのを聞きたい?市民研活動日誌原子力安全規制とコミュニケーションOECD/NEA |

おすすめSocial issue キーワードの例新着情報
・決定しきい値(決定限界) 最終更新記事
・リスク・コミュニケーション risk communication 記事一覧アクセス数トップ10
・ホット・パーティクル hot particle |
|
|
更新日:2021年09月01日 登録日:2014年03月11日 | ||
|
スマートフォン | デスクトップ |
||
| © 2020 国立保健医療科学院 Some Rights Reserved. | ||