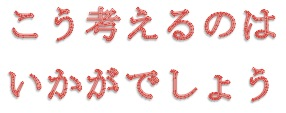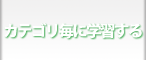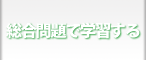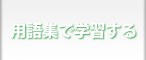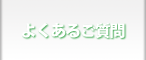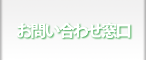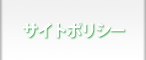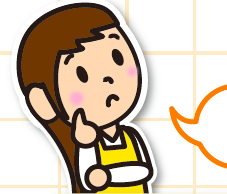解答結果
あなたの解答
物品のスクリーニング
次の文書は正しいですか?
『物品のスクリーニングでは、一箇所で放射線の計数率を測るだけでは、それを扱うことのリスクは推計困難なことがある。』
解説文
| |
|
 |
場所の線量や個人の線量だけじゃなくて、計数率(cpm: count per minute=一分間あたりの数)の測定も大切な気がする… |
 |
どうしてですか? |
 |
線量として小さくても、放射性物質がそこにあることを知るのが大切な気がする… |
汚染を持ち帰りたくない思い
| |
|
 |
「放射性物質がそこにあることを知る」のが大切だと思うのはどうしてですか? |
 |
一時帰宅から戻った先に放射性物質を持ち込みたくないという思いがあります…。近所でお世話になっている方に心配をかけたくありません。 |
 |
その心配りがあれば十分では… |
 |
スクリーニングに従事している方の安全確保も気になります… |
どの程度汚染するのか?
| |
|
 |
データも確認したいです。雨天の方が車への放射性セシウムの付着が少ないと噂になっています |
 |
警戒区域内の車両走行に伴う放射性物質による影響調査についてが出典ではないでしょうか |
 |
高圧の水をかけてもきれいにならないだけではなく、スクリーニング場で働いている方の放射線安全が確保されているのか?という疑問があります |
 |
測ってみるとよいのではないでしょうか |
 |
この測定はシーベルトではなくcpmであるべきだと思う |
 |
放射性物質の量を知りたいからですね |
 |
cpmの数が多いと付着している放射性物質が多いと思う |
 |
面積はどうですか?同じcpmでも、広い範囲で計測されるのか、一部だけで計測されるのかで量が違うと思いませんか? |
 |
それは当たり前で面積も重要だと思う |
 |
cpmとリスクの関係はイメージをつかめていますか? |
 |
数が多いと駄目な気がする |
 |
どれくらい数が多いと駄目ですか? |
 |
よくわからない… |
シーピーエムからベクレルへ
| |
|
 |
では、10万cpmの場合を考えてみましょう。どの程度のベクレルになりそうですか? |
 |
cpmは一分間に何個放射線が飛んでいるかだと聞いた気がする… |
 |
そうですね。例えば、60 cpmだと1分間に60個の放射線を数えているので、1秒あたり1個の放射線を数えていることになります |
 |
ベクレルは一秒間に一回と聞いた気がする |
 |
そうですね。ベクレルは一秒間に一回の放射性壊変(例えば放射性セシウムはバリウムに変化します)があることを示しています。放射性壊変時に放射線が飛んできます。一壊変で何個放射線が飛んでくるかは、核種によっても違うのもややこしいところです |
 |
放射線の話はややこしいことばかりです… |
 |
話を戻すと、10万cpmは約1.7 kcps(キロ count per second)になります。放射線は四方八方に飛びますので、そのうち半分を計測していると仮定し、一壊変で放射線が1個でると仮定すると、毎秒3千4百回程度の壊変があることになります。 |
 |
半分の放射線を数えると仮定すると、10万cpmだと3千4百ベクレル程度ということですね。この測定器で測っている範囲はどの程度ですか? |
 |
口径5cmφのGMサーベイ・メータが想定されています |
 |
口径5cmφだと面積は20cm2ですね。だとすると170 Bq/cm2と言うことね |
 |
表面汚染密度から計数率の換算は、核種、汚染面積、検出器のサイズなどに依存しますが、このような計算により、口径5cmφの標準的なGMサーベイ・メータでは、I-131の場合は、40 Bq/cm2が概ね13kcpmに相当するとされています。 |
| |
|
 |
なるほど、こうやってベクレルを出すのですね。ここからシーベルトを出せますか? |
 |
食べてしまった仮定で計算することができます。例えば、10万cpmの場合に、100cm2の範囲のCs-137による表面汚染を誤って経口摂取した場合の線量は、3歳児を仮定すると実効線量換算係数が2.1×10-08[Sv/Bq]であることから、170Bq/cm2×100cm2×2.1×10-08≒0.4[mSv]となります。 |
スクリーニング基準は適切?
| |
|
 |
帰還困難区域内から持ち出せるものは、スクリーニングを受けて基準値(13,000CPM)を下回るものとなります。※安全性が確認できておりませんので、食べ物、飲み物、薬品、化粧品など、体に直接入るものや触れるものは、持ち出しをお控えください。※屋外にあったもの、動物(ご自身で飼われていた犬・猫以外)は、持ち出しをお控えください。※外気にさらされたものは、線量が高くなる可能性があります。持ち出しをお控えください。 とありますが、13,000cpmが基準だと放射性セシウムをそれなりに含む土がどんどん持ち出されてもよいというメッセージに思えてしまう… |
 |
リスク管理として何を目的にしているかよくわからないということですね |
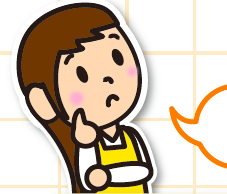 |
定量的に考えないと、初期のスクリーニングと同じような混乱をもたらすものとなりそう… |
 |
スクリーニング基準を下げた方がよいのではないでしょうか |
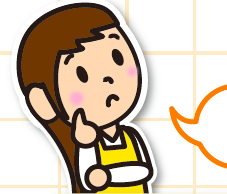 |
経口摂取するものであっても密封されていて、中に含まれる放射性物質の量が少ないことが確認でき、容器の除染が容易な場合には持ち出してもよいのではないかという意見がありました |
 |
複雑な気持ちになります。食べ物だと気持ちの問題がより大きいのかもしれない… |
 |
トレードオフに帰着するとも思えますので、この記事も参考にして考えて頂けるとよいのではないでしょうか… |
気持ちの整理をどうするかという難問…
| |
|
 |
車のスクリーニング結果から線量が推計できると言うことですね。車の汚染のcpmはここまで大きくなくて、それを全部口にするということもないので線量はこれよりも小さくなると思うけど、何となく気持ちが悪くて、受け入れられないという思いがある… |
 |
様々に交錯する思いですね |
 |
一時帰宅の途中では結構、線量率が高い地域を通りますので、その時には車の窓をしっかり閉めて空調も止めてあまり息をしないようにしています |
 |
毎時30マイクロシーベルトの区間が1kmだとして、時速30kmでの走行だと、その区間通過で受ける線量は、1マイクロシーベルトになります |
 |
どの程度吸い込むかは、既に調べられていますが、納得できなければ自分たちで測ってみるのもよいのではないでしょうか |
自己責任として真の責任の追求を放棄しているのではないかとの思い…
| |
|
 |
功利主義の話に持っていくのであれば、前提として公平性を担保して欲しい |
関連記事
空気中の放射性セシウム
劣化したGM管を廃棄する場合の注意点
- 細かな破片が飛び散りるので飛び散り防止が必要
- プラスドライバー等で割る際に大きな破裂音が発生するのでその対応が必要(ガムテープで膜の外側を養生することは有益)
参考資料等
公益目的での一時立入りについて
双葉町
富岡町
経済産業省
警戒区域内の車両走行に伴う放射性物質による影響調査について
原子力災害現地対策本部
原子力被災者生活支援チーム
国道114号、県道34号及び県道49号の帰還困難区域の特別通過交通制度の適用について
常磐自動車道 常磐富岡IC~浪江IC開通に伴う 帰還困難区域の特別通過交通制度の対象ルート追加及び 国道288号~県道35号の通過に係る同制度の運用変更について
運送業界向け資料
公益社団法人全日本トラック協会輸送事業部長 礎 司郎(放射線取扱主任者).いま物流に求められる放射線管理の基礎知識!(知っておきたい放射線の基礎知識!)平成26年4月1日(火)(pdf file: 3.7MB)
環境省
除染チーム
「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)」の公表について(平成27年3月30日)
帰還困難区域内の国道 6 号及び県道 36 号における除染の結果について
原子力被災者生活支援チーム
常磐線(富岡駅~浪江駅間)の空間線量率調査結果について(平成27年1月28日)
常磐自動車道(常磐富岡IC~浪江IC間)及びならは PA の線量調査結果について-開通前の最終確認結果-(平成27年2月27日)
県道256号等の帰還困難区域の特別通過交通制度の適用及び国道6号等一部路線における二輪車への同制度適用について(令和2年1月30日)
NEXCO東日本
常磐道の通行について
(1)常磐道を自動車又は自動二輪車で通行する人の被ばく線量
自動車で浪江ICから南相馬IC間を時速70kmで1回通行する場合の被ばく線量は、0.067μSvであった。
自動二輪車で常磐道浪江ICから南相馬IC間を時速70kmで1回通行する場合の被ばく線量は、0.083μSvであった。
(2)事故又は故障等により車外に1時間待機したとした場合の被ばく線量
常磐道(浪江IC~南相馬IC間)で車外に1時間待機した場合の被ばく線量の最大値は、1.8μSvであった。
(3)浪江ICの料金収受員の被ばく線量
料金収受員の標準的な勤務パターンに基づく被ばく線量は、1勤務あたり2.0μSvであった。
内閣府
オフサイトの防災業務関係者の安全確保に関する検討会
物資の緊急輸送に携わる方などの安全確保に関しても検討されています。
避難者の想い
想い.com
スクリーニングレベル設定
証言例
福島県のスクリーニングレベル引上げについて
OFC医療班における初期の活動、除染基準引上げに係る助言について
議論例
緊急被ばく医療の汚染管理レベル-その2
解説記事
体表面のサーベイメータによる測定での除染の基準はどうやって決まっているのですか?
対応例
立崎 英夫, 一時帰宅の現状から, 保健物理, 2011, 46 巻, 3 号, p. 215-218, 公開日 2012/07/28, Online ISSN 1884-7560, Print ISSN 0367-6110
福島県LPガス協会
東日本大震災への対応
LPガス容器の安全確認やLPガス容器等の汚染状況についても調査されています。
環境省
LPガスボンベの残ガス処理業務
原子力被災者生活支援チーム
避難指示区域に残置されているLPガスに含まれる放射性物質量調査結果について
JANES
避難指示区域に残置されている危険物等の放射能の確認手法について
社団法人 日本空気清浄協会
放射性物質で汚染されたエアフィルタの取り扱い指針
物品のスクリーニング一般
経済産業省
事業者向け支援
輸出事業者の方へ
外務省
東日本大震災・復興関連情報
原子力発電所の安全確保・我が国の輸出品に対する諸外国の規制等に対する取組み
国土交通省
港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン
日本貿易振興機構
国内の放射線検査機関(全国対応)について
日本商工会議所
非放射能汚染に関する証明への対応について
車両への放射性物質の付着
国道288 号及び国道114 号を走行した車両への放射性物質の付着状況
スクリーニング場の運営
浪江町
自らの責任において、適切に実施する
原子力災害現地対策本部
スクリーニングについては、あらかじめ定めた実施場所において、原子力安全委員会の助言を踏まえ実施する。スクリーニングの結果、基準値を上回った場合には除染を行うものとする。
汚染廃棄物対策地域内の廃棄物の処理に関するQ&A
警戒区域及び避難区域の見直し後に帰還困難区域になった区域から持ち出
す物や車両は、スクリーニングを受ける必要があります。このスクリーニングにより、表面汚染濃度が 13,000cpm 以上の物や車両については、これらの 区域外への持出しが禁止されています。
東京電力株式会社
構内外車両スクリーニングの合理化等について(平成27年2月23日)
港湾における中古自動車等の放射線の状況等について
関連情報
オフサイトの防災業務関係者の安全確保
日本保健物理学会
【解説】 現存被ばく状況における汚染した物の搬出のためのガイドライン
誘導したガイドライン値とその誘導の根拠が記載されています。最適化の観点で住民に役立つ情報提供も求められるところだと思います。
IAEA
原子力事故後の現存被ばく状況での廃棄物の扱いに免除の概念を日本が導入したとして例示しており、その例示に運用上の管理として表面汚染測定を組み合わせていると説明しています。
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Application of the Concept of Exemption, IAEA Safety Standards Series No. GSG-17, IAEA, Vienna (2023)
サイト内

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Application of the Concept of Clearance, IAEA Safety Standards Series No. GSG-18, IAEA, Vienna (2023)
|